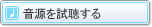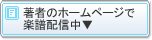第30回「悲しき小さな歌」
『エスキス』が、曲集としてよくまとまった印象を人に与える大きな理由としては、調性の並べ方や構成の上手さが挙げられる。4巻それぞれの最初の曲と最後の曲の雰囲気が、はっきりした意図に基づいて決められているのではないか、ということについても第25回の記事で述べました。
しかし、そんな大掛かりな計画性もさることながら、ある曲と次の曲のつながり方を聴いただけで「お、そうくるか」と感心させられたりすることも多いのです。中でも、対照的な部分がうまい具合に強調されて、アルカンの引き出しの多さを実感できるような箇所が面白い。
たとえば第1巻「スタッカーティッシモ」「レガーティッシモ」の対比であったり、「叱責」「嘆息」の流れであったり。第2巻なら「死にゆく者が貴殿に挨拶を」と「無垢」の並びなどにはぞくっとさせられます。
前回の「熱狂」から今回の「悲しき小さな歌」への受け渡しというのはそんな中でも特に秀逸なのではないか。もちろん、明るい元気な曲から悲しい曲への対比、なんていうのはベタではある。けれど、よく見てみるとアルカンの非凡な部分が浮き彫りになってくるように感じられます。
まず「熱狂」という曲、これが実はかなり特殊。普通ならこの曲は、ff の分厚い和音なんかで華々しく終わってしかるべきなんじゃないでしょうか。ものすごいテンションで始まっておいて、最後はなんだか落ち着いて終わる、などという構成は、こんな短い曲ではそう簡単に実現できるものではないのです。
「熱狂」の終わりがそんな風なので、続いての「悲しき小さな歌」はこの上なく自然な流れの中で弾き始めることができます。もし「熱狂」が当たり前のようにff の和音で終わっていれば、熱狂が冷めた余韻は、曲間で奏者が独自に作り出さなければいけない。一般的にはそれで何の問題もないのですが、しかし、アルカンはもうひとつ上のレベルで曲間をコントロールしているのです。
ついでに言うと、「悲しき小さな歌」の終わり方もちょっと特殊です。最後だけ伴奏にスタッカートが表れて、旋律は主音から属音へと5度跳躍の上行形で終わる。これも凡人には書けないものだと思う。悲しい歌なんだから、最後は沈んで行って、旋律は下行しながら主音に落ち着いて終わりたくなる。しかしアルカンはそんな当たり前のことはやらなくて、最後は微妙に浮遊させる。これだけのことで、悲しみが腑に落ちたとか、納得したとか、諦めてちょっと前を向いたとか、そんなごく微妙な心境が伝わってくるマジック!
何かの気分を表したくてごく短い小品を書く場合、ついついそのピークだけを切り取ってしまうのが人情というものでしょう。熱狂なら熱狂の頂点を、悲しみなら悲しみのどん底を歌にするのが凡人の思考です。でも、アルカンはこんな小さな曲を書くときでも、切り口がいつもちょっとだけずれている。熱狂なら、ちょうどピークから始まって冷めかける辺りまで描く。悲しみなら涙を拭って微笑む瞬間までを描く。
だから彼の音楽は短い中にも感情の動きがよく表れてくる。人が生きていく時間の流れを感じさせてくれる。1曲1曲の中にそうした躍動する流れが見えるからこそ、曲のつながり方の中にもハッとさせられるような新鮮さが生まれてくる。きっとそういうことなのだと思います。
音楽とは時間の芸術だとはよく言いますが、こんな短い曲の中でその時間の経過を見事に活かし切る作曲家はなかなかほかには見当たらない。『エスキス』が、数多ある小曲集の中でもダントツに「退屈しない」曲集である理由は、収録曲のバラエティの豊かさだけでなく、1曲ごとの時間の使い方の上手さの中にも隠されているのかもしれません。
演奏に際して。最小でも4小節単位のフレーズをひとつの波としてまとめられるように努力すること。伴奏となる刻みの和音も、1音1音別の声部として捉え、それぞれの声部をレガートで演奏しているつもりで弾きましょう。こういった音楽を演奏するときこそしっかり腹筋に力を入れて、呼吸もフレーズに合わせて長くしなければなりません。息が少しも苦しくならないようなら、その演奏はダメだと思った方が良いですよ!
それではまた。次回は「四重奏の冒頭」です。