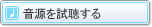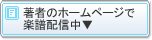第10曲「叱責」
ポップスの歌を作るとき、「曲先」と「詞先」と二通りのやり方があります。ロマン派の時代の歌曲というのは絶対的に「詞先」。まず詩人がいて、その作品を読んで作曲家が曲をつけた。
ところで、歌詞のない、インストゥルメンタルの曲の場合にも、似たようなことがある気がします。「曲先」......はそのまんまとして、「タイトル先」なんていうのがありそう。まずタイトルやテーマを決めて、それに即して作曲をする、と。劇伴音楽なんかを作る場合にはこういうことが多そうです。ロマン派の時代の器楽曲は、不思議なことに歌曲とはまったく逆で、「タイトル先」なんてのはおよそ見当たりません。もっとも、タイトルをつけること自体が珍しかった、というのは散々これまでにも述べてきましたが。
今回は、アルカンは「タイトル先」を結構やっていたんじゃないか、というお話。
さて、前回の「ないしょ話」について、この曲はメンデルスゾーンへのオマージュだろう、というようなことを書いた。性格的小品集というものについて語るなら避けて通れないのが、彼の『無言歌集』だ。その無言歌集とアルカンのエスキス、比べてみると、かなり共通点があるように見えます。
両方とも48曲からなる(アルカンは、最後に番号なしの49曲目がありますが)。そして、すべての曲にタイトルがついている。長い期間に渡って書き溜められたものである――等々。もしかすると、エスキスという曲集自体が、メンデルスゾーンへのオマージュなのでは? と思えるほど。
......でも、よく見るとこれらは表面的な共通点です。無言歌集が48曲なのは、6曲ずつ8巻に分けて出されたものだから、としか説明のしようがないけれど、エスキスの曲数は調性と深く関係したものだ。それに、6曲ずつ年を隔てて出版された無言歌集と違い、エスキスは全部まとめてからいっぺんに出版されている。49曲そろって初めてひとつの作品なんだ、という強い意識が働いていたことがわかります。
タイトルについて言えば、無言歌集の表題はそのほとんどが出版社によるもので、エスキスのように作曲者本人がつけたわけではないのです。「曲先」もいいところですね。
実は、アルカンは、エスキスよりもっと無言歌に似た小曲集を作っている。『歌曲集』と銘打たれた、6曲ずつの5巻からなる作品群です。これこそ、メンデルスゾーンへのオマージュとして位置づけるべき曲集です。
無言歌も歌曲集も、「歌」であるだけに、滑らかに動くメロディーがあって伴奏があって......という基本的な形を大きく踏み外さない。こういった音楽を弾くとき、タイトルについて考える必要性はそれほど高くないと私は思う。旋律を自然に歌えば、わかりやすく、豊かな音楽がそこに広がってくるからです。
しかし、エスキスはそれとは様子が違う。ここでは、タイトルが非常に重要な役割を果たします。題名がわかってこそ、曲の面白さや価値が100パーセント伝わってくるような曲がたくさんある。たとえば、私は第1曲の「幻影」について、連載第1回で「暖かな旋律の中にひんやりとした孤独を閉じ込めたような」などと書きましたが、これ、タイトルがなかったら「ひんやりとした孤独」を掴み取り損ねていたんじゃないかと思わなくもない。音楽だけ聴くと、満ち足りた響きに聞こえる。でも、その満ち足りた響きが「幻影」だから、そこに寂しさを見出すことができる。
今回の曲など、もっと直接的です。曲のゴツゴツした雰囲気は間違って受け取ることは不可能なほどはっきりしてますが、そこに「叱責」と題名がつくと、それがあんまりぴったりなので笑いが出てくるほどです。これはやっぱり、曲を思いついたので書きとめて、それからお似合いのタイトルを考えた、という世界ではないと思う。「叱責」の場面を思い浮かべていたら曲が出来上がった、ということに違いなくて、ならばタイトルは曲が完成する前から決まっていたわけだ。
だから、エスキスに関しては、タイトルの重みは相当だ。弾くにしろ、聴くにしろ、タイトルと曲の関係性を面白がっていたい。
「叱責」を演奏する上での注意点としては、とにかく音に勢いが欲しい。上から落ちてくる形のアルペッジョは、手首を利用して一気に弾きましょう。とはいえ、音の粒はきちんと聞こえるべきです。8小節目から左手に出てくる5連符は、5つでひとつの音符、くらいのつもりで弾くと弾きやすいでしょう。5の指の連続する指遣いは理不尽に感じるかもしれませんが、拍ごとのアタックを表現するには間違いなく最適です。手首を柔らかくしてその瞬間に手をうまく持ち上げてやることで対処しましょう。
ではでは、次回は「嘆息」です。