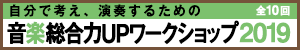フェスティバル実行委員長 播本枝未子より | 土田英介先生 インタビュー
「音楽家」精神を持つ二人の鬼才をむかえて
私自身は、あまり取り上げられないハイドンという作曲家に光が当たるのを大変楽しみにしています。2009年はハイドン・イヤーでしたが、今ひとつ盛り上がりに欠けました。日本人の苦手とする「ユーモア」や「意外性」は、ハイドンの扱いを難しくし、日本人のハイドン観を狭めてしまっているのかもしれませんが、この講座によって、一石を投じられるのではないかと期待しております。そこから、ベートーヴェンにつながる道がおのずと示されるのでは??というのが、私のこの企画へのねらいとするところです。
そして何より、レヴィン先生・土田先生という、演奏家と作曲家という二つの側面を持つ、現代の超一流の「音楽家」であるお二人から、「生きた分析」を伺えるのが楽しみでなりません。それこそまさに、ハイドンやモーツァルトが生きた時代の「音楽家」像そのものだったでしょうから。
土田先生に、今回の講義の聞きどころをインタビューしましたので、フェスティバルに向けてのイントロダクションとしてお楽しみください。

T:はい。今回のお話をいただいてから、改めて分析に取り組み、どうしたら短時間でハイドンとモーツァルトの音楽の面白さを皆さんにご紹介できるか、考えを練っているところです。特に、ハイドンについては、あまり取り上げられない初期のソナタも含めて、ソナタ全曲に目を通し、ハイドンの音楽を特徴づける要素を整理し、私自身が勉強しなおしています。
T:もちろん詳しくは8月24日当日にお話ししますが(笑)、かいつまんで申し上げますと、彼の音楽が持つ「意外性」ということになりますね。ハイドンは、凡庸であることを嫌い、常に大胆で面白い表現を求めており、表現をある意味で突き放し、「演出」するので、極めて男性的であって、センチメンタルな音楽にはなりません。
また、「固執」というのもひとつのキーワードになるでしょう。例えば、テーマのあるひとつのリズムに注目し、それにこだわって長く続けていくのですが、ベートーヴェンのように深刻にはならず、すぐにおとぼけや知らん顔をして、笑顔で締めくくってしまうのです。そういった例を、たくさんご紹介していきます。
T:彼の音楽はとても演劇的(オペラ的)で、ハイドンと対比すると、1つのテーマやモチーフへの「固執」ではなく、常に「新しいもの」を求める作曲家であることが鮮やかに浮かび上がります。ですから、テーマの数が多く、1つのパターンの持続は短く、投げかけと受けがとても多い、ということが言えます。
また、作曲家自身が音楽の中に入りこんで、自らに酔いながら曲を進めていく性格のようで、このあたりも、ハイドンと見比べていくと非常に面白いですね。
T:どの作品を取り上げる、というのはまだ最終的な決定ではないのですが、おおむね次のように考えています。
まず、ハイドンのソナタHob.XVI/50(ウィーン原典版第60番)第2楽章と、モーツァルトのソナタKV310の第2楽章を比較することで、先程申し上げた2人の作曲家の性格や技法の違いを端的に説明していきたいと思います。
その後、より情報量の多い曲として、ハイドンのHob.XVI/48(ウィーン原典版第58番)の第1楽章を取り上げ、彼の音楽の「意外性」「固執」などを検証していきます。ハイドンの音楽の「普通でないところ」を、敢えて「普通に作曲したら?」という実験も考えています。
対してモーツァルトは、選曲は未定ですが、例えばソナタKV333の終楽章をコンチェルトとして演奏するなど、「オペラ的」「対比」の要素を実証していきます。
最後には、冒頭の実例に戻りながら、「ではハイドンとモーツァルトの技法をを入れ替えたら?」といった試みをして、2人の作曲家のユニークな性格を鮮明にし、レヴィン先生の講義につなげていきたいと思います。
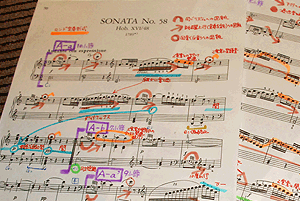
土田先生が分析中の楽譜/何色ものペンで書き込みがびっしりこれが当日の配布資料に発展する
取り上げる作品は、カラーで楽譜に分析(書き込み)をした今回の講義のためのオリジナル資料にまとめて、聴講にいらしてくださる皆様にお配りしようと準備しています。