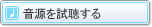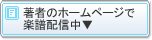第12曲「小舟歌」
言葉と同じで、音楽にも文法や語彙というのがあります。それらの規則に従うと、言いたいことがより正しく伝わる場合も多い。だからこそ作曲家は音楽理論の勉強をしなきゃいけないわけです。しかしこの文法や語彙、どの程度が生得的なものでどの程度が文化や教育によるものなのか、判断するのはかなり難しい。
たとえば、「協和音」がきれいな響きに聞こえるのは周波数の比率という物理的な根拠がある。不協和音より協和音を美しいと感じるのは、生得的な色合いの濃い現象に違いない。しかし、12平均律がいちばん自然な音階に聞こえてしまう現代の我々の耳は、明らかに西洋文化が世界中に広まる中で作られたもの。世界中の音楽が平均律に席巻されたおかげで、アラビア音階やガムランのスレンドロ音階といった物を曲中にちょちょいと用いただけで、異国情緒たっぷりの響きになる。この「異国情緒」は、生得的に感じるものではありえません。
作曲家はこれらの文法や語彙を、生得的なもの、非生得的なものに関わらず、自分の好みで使うことができる。中にはとても限られたコミュニティ内でしか通用しないような語彙だってあるかもしれません。でも、そのコミュニティの人にこそ聴いて欲しいのなら、そんな変わった語彙をむしろ率先して使ったほうが良いかもしれない。
ただ、生得的な根拠というものが薄れれば薄れるほど、その語彙がコミュニティ外や後世にも理解され、伝わっていく可能性も薄れる。何かの引用に意味をこめよう、なんていうのはその最たるものでしょう。勉強しないと読み解けない意味が隠されていることによって、より作品の深みが増すということもあるけれど、伝わる相手が少なくなる危険もあります。
ここまで第1巻を通して見てきた読者の方々は、エスキスがいかにバラエティに富んだものであるか、もう十分おわかりいただけていることと思います。アルカンという人は、語彙がとてつもなく豊富だ。誰それのパクリ、みたいなこともしょっちゅうやっているのだけれど、それは自分の言葉がないからじゃなくて、色々な人の言葉を解することができたからこその芸当でしょう。
そして、彼の豊かな語彙の中には当然ながら「生得的」に近いものもたくさん含まれている。それらは誰にでも理解しやすいのだけれど、彼以前には誰もピアノ曲の中で使おうとしなかった語彙だったりするので、聴き手は斬新で面白い表現として楽しむことができるのです。
たとえば今回の「小舟歌」の、オクターブずつ高くなりながら消えていく儚く不思議なエコーなど、問答無用で感情を揺さぶります。スペクトラルディレイなんていうサウンドエフェクトが当たり前のように存在する現在なら、これが「音楽」の語彙としてどれほど機能するかは誰でも理解できるし、簡単に使うことができる。でもそれをピアノひとつで効果的に聴かせるには、神経を研ぎ澄ませて、自分の心の中から新たな語彙として見つけ出してくる必要があったはずです。
アルカンの小品に触れるとき、いわゆるクラシックの言葉が聞こえてくるとばかり思っていると、いろいろとニュアンスを捕まえ損ねることになりかねません。耳を自由にして、ただ音をありのままに楽しんでみる。そうすると、本当に、思いもかけない色彩を目の当たりにすることができるかもしれません。
それでは「小舟歌」という曲自体について触れておきましょう。曲集の〆に「舟歌」を持ってくる、というのはメンデルスゾーンの『無言歌集』に感化されたものだろうか。いずれにせよアルカンが「舟歌」に特別な感覚を抱いていたことは確かで、たとえば『歌曲集』と名づけられた5つの小曲集はすべて、終曲が舟歌になっています。「小舟歌」がこの位置に置かれているのも、ここまでの12曲でひとつの区切りにしようという意思の表れでしょう。それは曲の終わりに記された "Fin du 1er livre." の文字からもはっきり読み取ることができる。
演奏上の注意。右手は常に、かすかな水面の反射をイメージするように優しく弾きましょう。和声の進行は、それ自体で音楽を展開させる力としてより、色合いが移ろいゆく様子を写したものとして捉えたほうがこの音楽に似合うでしょう。左手の積み重なるエコーの最後、 p みっつの音色には最大限の神経を使いましょう。
さて、こうしてなんともいえない感傷的な色合いで幕を閉じた第1巻でしたが、第2巻はこの色合いを引き継ぎ、まさにタイトルからして感傷的な「追憶」での幕開けです。どうぞお楽しみに。