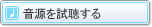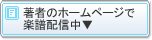第13曲「追憶」
さて、エスキスも今回の「追憶」からいよいよ第2巻です。第1巻がハ長調からだったので、第2巻はハ短調から。......え? と思われた方は、この連載の第8回の調性の話をちらっと見直してみてくださいませ。
その第8回では、調性の組み合わせが第1巻と第2巻で裏表のような関係であり、そのことで色合いの違いが実現されているのだ、というようなことを述べました。実際、巻ごとに受ける印象ははっきりと違っていて、4分冊にしたアルカンの意図は大成功している――と私は思う。
しかし当然ながら、調性がいくら工夫されていようとも、それぞれの曲に十分な特徴がないことには巻ごとの色合いなんて出しようもないわけで、構成の意図はもとより、各曲にこれだけの個性を持たせた作曲上のアイディアそのものを何より評価すべきです。
第1巻をここまで聴いてこられた方は、アルカンの音楽の幅広さというのをもう十分にわかってくださっていると思うのだけど、たとえばシューマンの『子供の情景』やショパンの『前奏曲』と比べてみれば、そこには歴然とした色合いの差がある。シューマンやショパンが、用いる色の数を限ることで個性を出しているのに対し、アルカンは用いる色の際限のなさがそのまま個性につながっている、とでも言いましょうか。
ロマン派の時代の音楽には、用いる語彙や文法はある程度お決まりのものに倣っておいて、それをどう捻るかによって精神性を表現する、というパターンが多い。もちろんアルカンもそういった音楽に取り組んでいる。ピアノのための『大ソナタ』などはその代表格。まあ、捻りが入りまくってすごいことになっていますが。
精神性うんぬんを重視しないタイプの気軽な音楽に関しては、サロンで演奏するのにちょうど良いように、奇をてらわぬ心地よさと優美さが第一。または、コンサートで観客を魅了するための派手なパフォーマンスが大事にされる場合もありましたが、いずれにしろ万人が違和感なく聴けるようにわかりやすい語彙、文法で書かれる。
ロマン派の作曲家たちはそういった環境の中で作品を書いたのだから、彼らの小品のほとんどが共通した語彙や文法にきちんと則って「美しく」作られたものになっているのも当然と言えるでしょう。
しかし、エスキスはまるでロマン派の曲集らしくない。むしろ実験的に好き勝手なことをやっていたバロック以前の音楽のノリに近い。なぜアルカンの書く曲集は、同時代の作曲家たちとこうも違っているのでしょうか。
それはアルカンの人となりを知ることでいくらかなりと得心できるかと思う。たとえば、彼がユダヤ人の家系に生まれ、敬虔なユダヤ教徒だったことなどもひとつの手がかりとなるかもしれません。ルーツは別の場所にあった、という点ではショパンにも通じますが、アルカンの場合は生まれも育ちもパリ。生まれたその瞬間から異邦人として暮らした彼の視点は、他人と違う場所にあったのかもしれない。
というような勝手な考察も含め、そろそろこの連載でも彼がどんな人物だったのか少しずつ紹介していきたいと思っています。
「追憶」について。この題材はアルカンにしてはいかにもロマン派に相応しいもので、悲しげな歌と暖かな思い出の対比からなる音楽内容も、この曲集中では相当ストレートな部類に属します。単旋律に和声づけがされ、響きが膨らむ17小節目からは各声部をすべてレガートで弾くつもりで。中間部は右手と左手が交差している上、右手は10度開く形なので弾きづらいかもしれません。声部の扱いという意味では記譜どおりに弾いたほうが好ましいのですが、右手の低い方の音を左手で取った方が合理的かもしれません。
それとこの曲、注意深く見れば和声法の禁則にある連続5度や対斜などが見つかります。が、響きの美しさはまったく損なわれていない。この辺りのアルカンの柔軟な理論の応用に注目してみるのも良いかもしれません。
それではまた次回、「小二重奏曲」をお楽しみに。