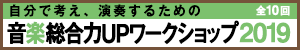第一線のピリオド楽器奏者ロバート・レヴィン先生による講座は、クラヴィコード、ハープシコード、フォルテピアノの実演を交えながら、ユーモラスにハイドンとモーツァルトの違いを解き明かしていった。楽器の変化と音楽の発展は密接な関係にある。そこで、鍵盤楽器の発達史を踏まえながら、ハイドンやモーツァルトがどのような語法で作曲をしたのか、当時の楽器が彼らの作曲にどんな影響を与えたか、18世紀音楽の会話のような要素とは何か、また指導に際してどのような点に注意すればよいか等、実践的な内容に踏み込んだ講義となった。ピアニスト・作曲家でもあり、現代作品の初演や委嘱などでも世界的に知られるレヴィン先生の世界。ここにその一部をご紹介したい。(当日の通訳は森泰彦先生)
ハイドンとモーツァルトは何が違うのだろうか?
まずレヴィン先生は同じ変ホ長調で書かれたハイドンのピアノ・ソナタ Hob.XVI:49と、モーツァルトのピアノとヴァイオリンのためのソナタKV481を比較。面白いことに第1楽章においては、ハイドンのフレーズは規則的、モーツァルトは不規則的。ついお互いの作風を取り違えてしまうほどである。しかし第2楽章では本来の特徴が現れる。ハイドンの第2楽章では、まさに本来のハイドンらしい素顔が垣間見え、モーツァルトのピアノソナタKV576第2楽章と比較すると、その違いは明らかである。
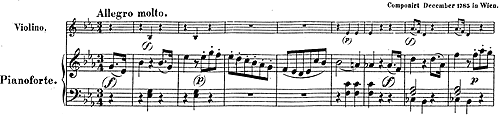
モーツァルトは常にフレーズが前に流れるような連続性が保たれているのに対し、ハイドンは間や沈黙を持って音楽に句読点をつける、つまりアーティキュレーションに特徴を持つ。ハイドンの作品では休符による「間」が、その音楽の中でもっとも生き生きした、ユーモアあふれる瞬間なのである。したがって賢い音楽家は、休符は次の音符が来るまで「待つ」時間ではなく、沈黙や間を意識的に「作る」のである。
顔の表情も豊かなレヴィン先生のデモンストレーション演奏は、ユーモラスなハイドンが現代にひょっこり蘇るような感覚をもたらしてくれる。ハイドンの「間」には、思わずくすっと笑ってしまうユーモアが隠れていることが確かに実感できる。
ハイドンの「驚きの演出」~その1 普通の形式を崩す

18世紀は音楽史において初めて、作曲家が自分が意図したように聴衆に理解してもらおうと試みた時代である。すなわち、<問い(4小節)と答え(4小節)>という形式を踏まえることによって、聴衆が音楽の行方を追いやすく、また音楽とともに呼吸をすることが容易くなった。その後ベートーヴェン、シューベルト、メンデルスゾーン、シューマンと時代を経るに従って音楽は主観的になり、<問いと答え>という形式も次第に薄れてきた。
ではその時代において、ハイドンはどのようなユーモアを音楽に盛り込んだのか?
ハイドンの弦楽四重奏 No.54-1第2楽章の冒頭4小節は、1小節目(伴奏)+2~3小節目(メロディ)+4小節目(伴奏)で、「いったい何が起きているのだろう?」という意外性と緊張感が漲る。冒頭8小節のうち、メロディ+4小節+伴奏4小節だが、それは前述の<問い4小節+答え4小節>という常套手段ではない。何回も肩透かしを食らうと、今度は騙されまいという気持ちになるが、するとハイドンは次の4小節を全く普通に進め、聴衆の予想を裏切ってさらなる「驚き」を演出する。そしていきなりフレーズが上行し、さっと収まる。
ハイドンのユーモアは決して大仰なものではなく、何食わぬ顔をしてさっと行なわれるが、これがハイドンの奇跡である。これを演奏者が理解し、聴衆にしっかり伝わるように演奏したい。
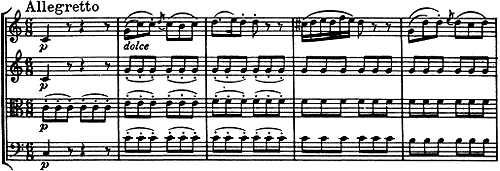
ハイドンの「驚きの演出」~その2 だんだんエスカレートする
ハイドンのユーモアは、次第にエスカレートする。ピアノ・ソナタ 変ホ長調 Hob.XVI:52では、第2主題への導入で調性が変わらないのに対し、第2主題の展開では遠隔調への転調を伴い、段々エスカレートしていくのが分かる。最初は少し動かすだけだったものが、次第に振り幅を大きくし、音楽に躍動感ある変化を与えている。
ハイドンの音楽の展開は、あたかも小さな出来事から次第に大きな災難を引き起こし、そしてある時、さも何事もなかったようにさっと手をはたく「ミッキーマウスのアニメのよう(笑)」とレヴィン先生。ハイドンの交響曲第103番第4楽章や、ファンタジアHob.XVII:4 ハ長調なども参照されたい。音楽は常に優雅に知的というわけではなく、秩序がなく雑然としていることもある。
こうしたフレーズの作り方は、後年ベートーヴェンに大きな影響を及ぼした。ベートーヴェンのピアノ・ソナタNo.7 Op.10-3(譜例)冒頭は、4小節-4小節-2小節でさっとフレーズが終止するが、さらに「だめだ!」と怒り狂って次のフレーズへ続く。
モーツァルトの転調と驚き、ハイドンとの違いは?
ハイドンとモーツァルトは、フレーズの収め方にも違いがある。レヴィン先生いわく「ハイドンが災難を引き起こした後、さっとどこかへ行ってしまうのに対し、モーツァルトは地球の果てまで行こうと、10秒で家に戻ってくる」。例えばモーツァルトのピアノ協奏曲No.17 KV453は、ロ長調からハ短調へ10秒で転調する。こうしたモーツァルトのメンタリティは、戦略的・表現法的にハイドンとは全く違うものである。交響曲第41番 ジュピター4楽章の再現部、モーツァルト幻想曲No.4 KV475の和声の変化などにも着目したい。
予想外の転調はハイドン、モーツァルトにも存在するが、ハイドンは聴衆を楽しませたり、挑発するために行い、モーツァルトは音楽に劇的な効果を与えるために行う傾向がある。こうした転調はハイドンの時代には例外的であることが多かったが、モーツァルトの時代には普通になった。
(注:なおハイドンはモーツァルト没後も10年以上作曲家として第一線にあり、今回呈示された例にはモーツァルト没後のものが含まれていることに留意されたい)
チェンバロ(ハープシコード)

ハイドン、モーツァルトが活躍した18世紀に主に使われていたのはチェンバロ(ハープシコード)で、その原型はフランドル地方で作られ、フランスで改良されたものが主流である。
ハイドンの鍵盤ソナタは、1770年以前の作品(それ以降の作品も一部含む)はチェンバロのために書かれたおり、強弱記号がない。また特徴として、数小節単位ではなく、大きなセクションごとに対照的なキャラクターが作られている。一方モーツァルトは処女作品であるソナタKV279から、ピアノのために作曲している。(モーツァルトが小さい頃はチェンバロを演奏していた)
当時の典型的な二段鍵盤チェンバロは3つのレジスターで構成されている。下の鍵盤に8フィートと4フィート、上の鍵盤に8フィートのストップが付いており、両鍵盤では弦をはじく位置が異なるため、上鍵盤の8フィートは鼻にかかったような音がする。打鍵のスピード、弦を弾くスピードが大変速いのが特徴で、その打鍵の繊細さを体感することによって、現代ピアノ演奏にも応用できる。
例えばハイドンの初期のソナタは、ディナーミク記号が現代ピアノ向けではないことを念頭において、ピアノの上でハープシコードのようなキャラクターを再現しなくてはならない。

●チェンバロ(ハープシコード):ブルース・ケネディ
●フォルテピアノ:ヴィーンのアントン・ヴァルター、ポール・マクナルティーによる複製
(東京音楽大学所蔵)
クラヴィコード
レヴィン先生演奏ビデオ
バッハ、モーツァルト、ベートーヴェンの時代にはクラヴィコードが存在し、これはチェンバロと異なるディナーミクを持つ楽器である。チェンバロは弦をはじいて音を出すが、クラヴィコードは鍵盤から薄い板状のタンジェントが垂直に弦に当たって音を出す。キーを押し下げるとタンジェントは弦に接触したままになり、ヴィブラートをかけることもできる。非常に繊細なデリケートな音が出るため、より深い親密な感情を表現するのに適していた。ベートーヴェンは後年聴覚を失ったが、クラヴィコードは生涯好んだという。
ハイドンのソナタ ハ短調 Hob.XVI:20はディナーミクが幅広くピアノのために書かれてはいるが、本来クラヴィコードでの演奏を想定していたのではないか。ここでレヴィン先生がクラヴィコードを演奏を披露。繊細で軽やかな、しかし奥深い心情を吐露するような音色が響いた。
(b)楽器を購入した弟子はDietrich Ewald von Grotthuss (1751~86)。返礼の作品は「ジルバーマン・クラヴィーアを受け取った喜び(Freude über den Empfang des Silbermannschen Claviers)」。YouTubeにクラヴィコード演奏ビデオあり!(情報提供:森泰彦先生)
ピリオド楽器の豊かな表情を、どうピアノで再現するか

レヴィン先生はさらに、ピリオド楽器と現代ピアノのメカニズムの違いに触れ、それがどのような響きの効果を生むのかを実証された。まず平行弦である昔のピアノは繊細な音が出るが、19世紀半ばにアメリカで交差弦が発明され、パワフルな音が出るようになった。平行弦では両手を同じ強さで弾けるが、交差弦はその楽器構造により、両手を同じ強さで弾くと左の音量が大きくなりすぎるため、米国の指導者は右手のメロディを取り出してさらうという練習法を実践した。結果として今日のピアノでは、右左どちらが重要かを演奏家が決定し、重要でないほうを弱く弾かなくてはならない。
モダン・ピアノは弦を数10トンの張力によって引っ張っているため、音が長く保持される。しかし完全に音が美しい音に到達するまで時間がかかることに、ピアニストの多くは気づいていない。打鍵すると弦が上下動し、それから横揺れになる。あまりスタッカートの練習を好まない学生がいるが、それは音が熟成する前に鍵を離さなければならないから。それがソフトペダルをよく使いたがる理由でもある。ソフトペダルを踏むと(中音域以上)3本→2本の弦しか叩かれないので、良い音はより大きく響く。
アクションは2方式あるが、モダン・ピアノにつながるイギリス式アクションの鍵盤楽器は、歌うように発声し、ラヴェル、ラフマニノフ、ブラームス・・などに適している。一方ウィーン式アクションの鍵盤楽器は、すぐに音が出て発声が速いが、張力が弱いので消えるのも速い。話すように発声し、ハイドン、モーツァルトなどに適している。
ハイドン:アンダンテと変奏曲」Hob. XVII:6
こうしたピリオド楽器がどれだけ表現力があるかを実証するために、レヴィン先生が演奏したのは、ハイドンの「アンダンテと変奏曲」Hob. XVII:6。(演奏ビデオ *本来はすべての反復を実施しその際に装飾するが、当日は時間の都合で反復を省略し、しかし時おり装飾する、と説明された)
この曲はハイドンが好んだ二重変奏形式で、長調と短調を行き来する特徴がある(例:ハイドン ソナタ ト長調 Hob.XVI:40)。ハイドンはもともとこれをソナタの第1楽章にするつもりで、冒頭にダ・カーポして終わるようにいったん書き終えたが、それから彼には何かが起こり、ハイドンの他の曲にはないような荒々しさと絶望のある長い終結部分を書き、これは明らかにベートーヴェンの熱情ソナタに影響を与えたと説明された。

C.P.Eバッハ著『クラヴィーア奏法』には、「演奏家が熱意を持っていなければ、聴衆は熱意を持たない」という一節がある。演奏家は自分が最も愛してやまない曲を選び、その曲のどこが好きなのかを見つけ、その中で自分自身を表現し、聴衆に伝えることが大事で、指導者はぜひそれを励まし啓蒙して頂きたい。演奏家が幸せであれば、聴衆も幸せなのである。
そして18世紀の音楽は、特にそのキャラクターに気を配ること。当時の人々は服装や動作、話し方など外見で人となりを判断した。もちろんショスタコーヴィチやラフマニノフの楽譜からもキャラクターは把握できるが、ハイドンやモーツァルトは楽譜上でより容易くキャラクターを読み取ることができる。
ゲームをするとき、ルールを知る必要があるのと同様に、18世紀の音楽にもルールがある。例えばスラーやスタッカートがどのように音楽を作り出すか。あるいは、アルベルティ・バスにスラーが書かれている時は5の指を押さえて指ペダルをする等。ペダルを使ってはいけないのではなく、必要なときに使うことを心得て頂きたい。
そして演奏で重要なのは、そのストーリーを語ること。ハイドンやモーツァルトは大変物語が好きであった。例えばモーツァルトではキャラクターがよく変化するが、メロディではなく伴奏に注目すると、キャラクターがどこで変化しているのかが分かる。
またピアノ指導に際して、「モーツァルトなど天才が書いた楽譜を、もし普通の人が書いたらどうなるか」という観点で考えるのもよい、とレヴィン先生自らフレーズの一部をに創作。すると、モーツァルトの楽曲が「良い」のではなく、「信じられないくらい素晴らしい」ということが分かる。また書かれてある音符を追うだけでなく、次に何がくるのかを想像してみてほしい。
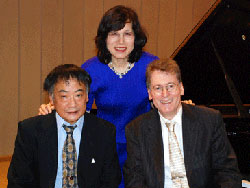
昨年はハイドン没後200周年でしたが、ショパン生誕200周年の今年と比べてその注目度の温度差は歴然としています。私は個人的にハイドンが大好きなので、没後200年でハイドンへの注目度がアップするか、と期待していたのですが、残念ながら肩透かしを食らった印象でした。それでは1年遅れてもハイドン音楽の面白さ、魅力をもっと知って頂きたい、という思いで土田先生と世界的なピリオド楽器奏者ロバート・レヴィン氏に講師をお願いしました。
レヴィン先生とはアメリカの審査で御一緒したことがあり、一昨年の演奏会でのフォルテピアノでのハイドンの演奏が素晴らしかったので、楽屋に行って早速お願いしたところ、超多忙な音楽家であるにも拘わらず思いがけず快く引き受けて下さり、演奏会の合間を縫って来日して下さいました。リハーサル時間も殆ど無い中でフォルテピアノ、チエンバロ、クラビコード、現代ピアノと4台の楽器を次から次へと見事に弾き分けつつ、交響曲、室内楽曲、ピアノ曲の間を縦横無尽に駆け巡ってユーモアたっぷりにお話して下さいました。ただ言葉の関係で、十分にレヴィン先生の意が伝わらなっかったのが少なからず残念ではありました。今回10年ぶりの土田先生の解析講義は、まるで天才的な外科医による執刀のような無駄のない見事な切り口で、会場の皆さんも大納得なさって下さったことでしょう。
毎回フェスティバルの度に、内容的に十分だろうか、皆さんに集まって頂けるだろうか、意義が伝わるだろうか、等々と緊張するのですが、今年は特に、この猛暑、ウィークデイ、夏休みで多くの学生が帰省している、など何重苦も重なり集客に大変気を揉みました。結果的に全国各地から551名の方々がお集まり下さり、猛暑の中、頑張ったフェスティバル委員の私達も報われた思いでした。ありがとうございました。日本の音楽教育発展のために皆様と共にさらに学んで行きたい、と考えています。




 br
br br
br