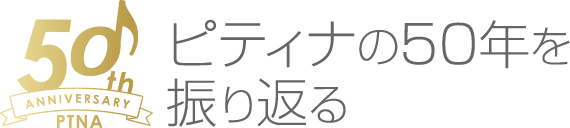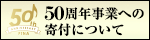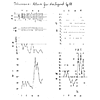
幼少期の教育が大事、という共通認識が広まるとともに、上級で必要とされる資質や技能をいかに小さい頃から育んでいくか、という逆算の考え方も少しずつ進んできたようだ。その一つが楽曲全体への意識。「秋山徹也先生の音楽通論研究 知っておきたい音楽の仕組み」(155号p30-32)、「佐藤峰雄のピアノ入門書研究」は対象は異なるが、楽曲構造の側面からいかに解釈するか、というアプローチがなされている。後者は、シューマンのユーゲントアルバムとバイエルとの違い、などを例に挙げている(161号p50-53)。
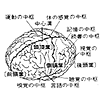
子供の発達段階に応じてどう指導すればよいか、人体力学や発達心理学などを踏まえた指導法の研究がなされ始めた(「手の構造と発達~早期教育に関連して」酒井直隆先生、213号p23)。また、脳科学的な研究報告もある。「作動記憶(ワーキングメモリ) 何かをする時に一時的に覚えている記憶。ピアノの場合だと、どのように演奏するかという記憶にあてはまる。単にある決められた音を弾くだけでなく、自分のイメージの中で表現しようということに使われる。・・この作動記憶が次の行動を起こす時に働き、実際に我々の生活を高めるのに大変役立っている」(「子供の身体と精神の発達について」久保田競先生203号p24-25)。 また「子育てに学ぶピアノレッスン」(185号p2-)、「導入から上級への上手な橋渡し ~中級をどうするか」(204号p21-)などの特集も組まれた。

1970年代に導入されたバスティンメソードはすっかり全国的な人気となり、会報でも「効果的なピアノ指導法 バスティンメソード」として連載が組まれた。その包括的・全人教育的な考え方は多くの指導者に影響を与えている(164号 p12--16ほか) 。音楽は教わる順番も大事。「ピアノの導入となると、「読む」「弾く」から始めてしまっているのではないでしょうか。・・音楽はそもそも歌と踊りのためにあるという原点に立ち返って指導すれば、子供の目は輝きを取り戻すのではないでしょうか。・・まず良い音楽を聴くこと、次に弾くこと、これは音感性として心に響く状態まで持っていくこと。そうすれば弾く意欲が出てきます」 (「音楽的基礎体力とは~聴く、歌う、 弾く」小湊功一先生、184号 p1)。またピアノを起点として、全教科へ広げていく考え方も。「ピアノを弾くことのみに留まらず、打ち破ってこそ新しい試みやアイディアが出てくるのではないでしょうか」(山?栄子先生、171号p38-39)。リベラルアーツの考え方が根底にある。

音楽文化の醸成や音楽的な環境作りなど、音楽をする個人だけでなく、環境そのものへの関心も広まってきた。レッスン室だけでなく、日常から音楽に親しむこと。その一つが、家庭での音楽鑑賞である。連載「音楽鑑賞の勧め」では、 ピティナ入賞者の親子(204号p50-51)や指揮者(206号p30-31佐渡裕氏)などが登場。またあるコンサートホールマネージャーは「国際コンクールはもちろん、国内コンクールでも大ホールでの演奏が要求されています。指導者がホールでの響きの聞き方、ホールで弾いた時の音のバランス、音量の聴き方も教えなければなりません」と、演奏環境の変化に言及している(211号p52-53)。この頃、ピアニストの聴き比べを楽しむ人も(「アシュケナージとポリーニを聴き比べ」151号p34-35、「NYピアニストたち」157号p18-19など)。
21世紀が目前に見えてきた1990年代後半。会報にも「21世紀」の文字が度々お目見えするようになる。 その頃、ピアノ指導者は20世紀をどう振り返り、新たな時代を迎えようとしていたのだろうか。(「21世紀を生きる子供達に良いレッスンを」バスティン公開講座リポートより、182号p70-71)