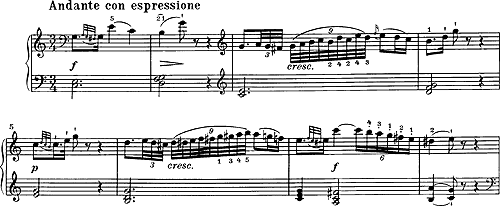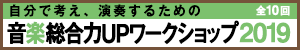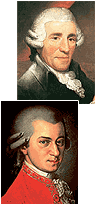
「ハイドンとモーツァルトは、似てるようでいて違う。でもいったい何が違うのだろう?」
誰もが持つ素朴な疑問に、真正面から取り組んだ今年のピティナ・ピアノフェスティバル。作曲家・ピアニストであるロバート・レヴィン先生、土田英介先生のお二人を講師にお迎えして、8月24日(水)東京音楽大学A館100周年記念ホールにて開催された。
前半に登場した作曲家の土田英介先生は、ユニークな視点で分かりやすい事例を引用しながら、鋭い楽曲分析を示して下さった。一方、古楽研究のエキスパートでもあるロバート・レヴィン先生は、ハープシコードやクラヴィコード、ピアノフォルテの実演も交えながら、ハイドンとモーツァルトの違いを生き生きと説明して下さった。お二人の講義から浮かび上がったハイドン像はユーモアにあふれ、モーツァルト像は人間味にあふれていた。そのフェスティバルの様子をダイジェストでお届けする。

土田先生はこの講座のために、ハイドン、モーツァルトのソナタはもちろんのこと、オペラ・交響曲・室内楽などあらゆる作品に目を通した上で、改めて両者の違いを明確に解明して下さった。それはたとえば、モーツァルトの主観性とハイドンの客観的表現を対比しながら、「ハイドンは演出家である」といった一言で的確に表現される。また、「もしハイドンがモーツァルトだったら、あるいは逆であればどうか」といった創作実験も盛り込まれた。当日配布された土田先生書き下ろしの特別講義資料は、500ページから削りに削って80ページにしたという力作!作曲家ならではの視点の鋭さで、ハイドンとモーツァルトという似て非なる両者の違いが浮き彫りになった。
ハイドンは「演出家」であり、モーツァルトは「主人公」である
ハイドンとモーツァルトは何が違うのか?土田先生はまずハイドンのピアノソナタNo.60 Hob.XVI/50 第2楽章と、モーツァルトのピアノソナタKV310第2楽章を対比させながら、下表のような観点からそれぞれの特徴を解明された。すると両者が実は異なる性質を持っていることが理解できる。
| ハイドン | モーツァルト | |
|---|---|---|
| 拍頭の倚音 | 少ない | 多い |
| フレーズの切り方等 | お茶目で常に笑顔 | オペラのアリアのよう |
| 表現へのアプローチ | 客観的な視点で表現を突き放し、大胆な工夫を凝らしている印象 | 自らが曲の中に入り込んで心情を訴えかけている印象 |
| S(D2)→D→Tの扱い | 朗らかさと大胆さ | いたわりある旋律 |
| 主人公の位置 | 作曲者以外である印象 | 作曲者自身である印象 |
なぜハイドンは「演出家」なのだろうか?
土田先生はハイドンの非凡性を、「奇数小節で構成されるフレーズ」に着目。そこで5小節のフレーズを4小節に、また9小節を8小節に、収まりのよい偶数小節のフレーズを土田先生自身が創作。そうして偶数と奇数を対比させると、1小節多い部分に込められたハイドンのユーモアや工夫に気づかされる。
たとえば、ソナタNo.58 Hob.XVI/48第1楽章では、冒頭~10小節目を8小節(4小節+4小節)に短縮することで、なにがハイドンらしさを作っているのかを考察。土田先生は、5・6小節目を省略した例と、8・9小節目を省略した創作例を挙げながら、前者はダイナミクスの変化(p→f)と跳躍上行の追加、後者は偽終止と間を、そのハイドンらしさの理由として挙げた。(譜例)
そして22小節目も、ハイドンの非凡性を表す1小節(譜例)。これを含む18小節目からの9小節は変化に富んでおり、まず跳躍上行はこれまでの9連符から14連符へ増加。20小節目で一気に駆け上がり、21小節目でアーティキュレーションと音価に変化を加え、22小節目突然f→ppへ、そしてまた23小節目fに戻すことで、ダイナミクスの変化も取り入れている。確かに22小節目を省いて8小節にすると、fのフレーズが続くことになり、驚きは少ない。
27~31小節目は、30小節目に下行とG音への固執が見られ、これが偶数小節では収まらない理由となっている。さらに奇数小節のフレーズはまだまだ続き、土田先生はそれをすべて偶数小節に短縮して書き直すことで、ハイドンのフレーズの面白さを明かしていった。
ハイドンの固執性は、音楽のあらゆる要素に現れている。「ハイドンが目を光らせたら大変!」と土田先生もユーモアたっぷり。
音のこだわり
ソナタNo.58 Hob.XVI/48 第1楽章(譜例)では、最高音、最低音、第6音などへの固執が見られる。冒頭からフレーズの最後はG音(アクセント付)で印象づけ、29・30小節ではフレーズの中でG音に固執し、32~34小節にかけては一気にフレーズが下行し、36小節目にはG音の最低音が登場する。
また主調C-ur、同主調c-ollの第6音へのこだわりは、47小節からの経過部分(c mollの第6音)、58小節からのテーマの変奏(C durの第6音)に現れている。114小節からは最高音へのアプローチが始まり、細かい音価とシンコペーションによる上行の末、116小節で最高音Fに到達する。そして今度はシンコペーションなしの十六分音符で下行し、120小節で最低音Gが再び現れる。その後も最高音へのアプローチは続き、再度C-durの第6音へのこだわりを示しながら、コーダで閉じられる。
第2楽章は、第1楽章で固執したG音(アクセント付)に続き、C-dur第6音から始まる24~26小節のメロディがモチーフとなる。
ソナタNo.44 Hob.XVI/29第1楽章では、当時の楽器における最高音と最低音へアプローチしている。87小節目の最高音Fから下行してコデッタへ至り、最後は最低音のFで締めくくられる。
リズムのこだわり
ソナタNo.47 Hob.XVI/32第1楽章(譜例)は、まさにリズム反復の連続!2小節目のリズム(Cis-D-H)が、38小節目から始まる第1主題の展開で、何度も反復される。しかもそれに飽き足らず、43小節目からはオクターブユニゾンとなり、48小節目で第1主題が再現されるまで9小節もしつこく続くのである。「状況は終わっているのに続ける面白さ、それがハイドンの固執なんです」と土田先生。会場からも思わず笑いが起こる。
アーティキュレーションのこだわり
ソナタNo.37 Hob.XVI/22第1楽章(譜例)では、H-dur属調へ向けて経過部で次第に上行していき、第2主題では16音符が続く。ここでアーティキュレーション、同じ音型などへの固執が見られる。土田先生は、「機嫌のよかったピアノの先生が、生徒が弾いているうちに、だんだん形相が変わってきて、そして最後には怒り出し・・(笑)」とユーモラスに表現。同じアーティキュレーションと16分音符の音型が続くからこそ、様相の変化がよく分かる。
(3度)進行へのこだわり
ソナタNo.39 Hob.XVI/24 第1楽章は3度進行に固執する。第1主題は両手とも八分音符の3度進行でメロディが進んでいく。と思っていると、8小節目では十六分音符の三連符で音価が軽やかに変化して、2拍目のD音でさっとフレーズが終わり、3拍目の間を作って余韻を残す。何かに執拗にこだわっていたかと思うと、さっと身を翻すようにそれが終わる。その落差がまさにハイドンらしさである。
ソナタNo.20 Hob.XVI/18第2楽章は、「F-Es-D」という音型が繰り返される(譜例)。土田先生は「ピティナ」という言葉をあてはめながらデモ演奏。すると冒頭~14小節で、実に5回の「ピティナ」が登場する。
なお、ソナタNo.54 Hob.XVI/40 第1楽章では、2度進行にこだわっている(78小節目~)。
固執することで何が起こるのか?交響曲も聞こう!
音楽の中のあらゆる要素にハイドンは意外性を追求している。間やフレーズの終了の仕方、音価・リズム・アーティキュレーションのこだわり、方向性(上行・下行)の強調、極端な音域の変化、同じ音型・音の反復、偽終止など、意図して意外性を演出している。
こうした意外性は交響曲や室内楽でも発揮されている。たとえばハイドンはピアノ・ソナタなどで急に分厚い和音を登場させることが多いが、これは交響曲において楽器の数を突然増やす、といったことにも共通性がある。また音色の変化にも着目したい。
意外性に富むハイドンのソナタ作品の中でも、意外性の連続なこの曲。同じ音(D)へのこだわり(12小節目~)、2度進行へのこだわり(78小節目~)、アーティキュレーションへのこだわり(81小節目~)、急な厚い和音から細かい音価で上行、急に音を少なくしてすっとぼけた顔して、最後は厚い和音で終わる(94小節目~)。
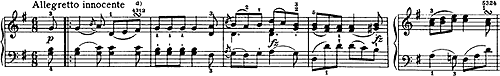
ある一つ(または複数)の要素に固執するかと思ったら、いきなりとぼける。それもハイドンの魅力の一つである。ソナタNo.58 Hob.XVI/48第1楽章(譜例)では、細かい音価での上行(6小節目)、ダイナミクスの大胆な変化(6~7小節)、そして一瞬の間を置いて、急に単純な終止型でフレーズが閉じられる。さらにここでもダイナミクスの変化(f→p→pp)が見られる。
また56小節目からのテーマの変奏においても、同じようなおとぼけが出現する。62小節目は32分音符が密集したフレーズで一気に盛り上げ、一瞬の間をおいて、64小節では巧妙に間を置きながらリズムを変化させて、最後にすっとぼけた表情を見せる。
ソナタNo.38 Hob.XVI/23第1楽章の再現部では、経過句をばっさりカットして走句の第2テーマへ入る。ソナタNo.37 Hob.XVI/22第1楽章では、同じ音型への固執(16分音符)を繰り返し見せるが、8小節目のフレーズの終わりでは、32分音符を2拍分登場させてさっと終わり、1拍の間を置く。
このように音価を急に変化させたり、リズムの変化や休符の配置によって、それまでの流れをさっと変えたり、何事もなくフレーズを終わらせたりする。
ハイドンの作品には、遠隔調への転調もしばしば登場する。 ソナタNo.62 Hob.XVI/52第1楽章では、68小節目においてc-mollからE-durに転調し、第2主題が展開する(譜例)。この遠隔調への転調はハイドンの交響曲などにも見られる。交響曲第98番第4楽章では、展開部へ入る時、一瞬の間をおいた後、F-durからAs-durへの転調がなされ、それと共にソロヴァイオリンの響きが聞こえるようになる(149小節目)。ピアノ・ソナタでも大胆な転調がなされる時は、転調後の音色感も大きく変化させるとよいのではないか、と土田先生はアドバイスされた。
特に、3度転調は初期の作品からよく見られる。3度転調とは和音の根音が長三度下にいく馴染みある転調(ショパンも多用)。ハイドンのソナタNo.38 Hob.XVI/23第2楽章(譜例)は、5小節目で半終止からの3度転調が登場する(f-moll→As-dur)。接続詞だと「ところで」という感じであり、状況と空気の変化が大事である。
ハイドンはまるでいたずら小僧のように、予想外のことをして、聴き手を楽しませてくれます。その意外性がよく出ている作品として土田先生がご紹介・分析されたのが、ソナタNo.44 Hob.XVI/29 第1楽章。変幻自在のリズムや音価、同じメロディや音型への固執、音域の幅広さ、思い切りの良さ、そういったあらゆる要素に注目し、驚きをもって聴いてみましょう。
ハイドンの面白みや新鮮味は、突然出現する思いがけない音響からももたらされる。交響曲第93番 第2楽章では、コーダ前の78~80小節目に着目。ヴァイオリンとフルートの掛け合いがppで優しく交わされた後、突然ffでファゴットの一音(笑)!そしてまたtuttiになりコーダへと進む。
この音響を再現するために、ステージ上に置かれたフォルテピアノを用いて、ソナタNo.59 Hob.XVI/49 第2楽章最低音のF(76小節目)を鳴らしてみる。そこにコントラ・ファゴットのような音を、意識して出しても面白く感じられる。