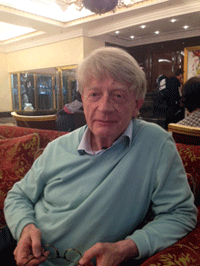チャイコフスキー国際コンクール(4)Interpretation(解釈力)を高めるには
クラウス・ヘルヴィッヒ先生インタビュー
日本人ピアニストでは福間洸太朗さんや梅村知世さん(2010年グランプリ)等、またセヴェリン・フォン・エッカルトシュタイン(2003年エリザベート王妃1位)など国際コンクール優勝者・入賞者も多く育てているクラウス・ヘルヴィッヒ先生(ベルリン芸大教授)。審査員の一人として演奏をどのようにお聴きになっているのか。また音楽を解釈することについて、お話を伺った。
ただ"ピアノを弾けること"には興味がありません。それ自体は何も意味しないからです。"ピアノを弾くこと"と"曲を解釈すること"は別です。解釈は人によって意見が違うでしょう。だから審査員が何人もいるのです。私が重視するのは、音楽がそこにあるかどうか。音楽を十分に理解して、その音楽を的確に表現しているか、自分の意見があるかどうか。音楽がまずあり、それに関して自らの意見を持っているかが大事です。強い意見があってもそれが音楽を無視したものであったり、自分を見せるために音楽を使う人もいますから。音楽の知識と敬意が必要ですが、それだけでは十分ではありません。ピアノ演奏にはあらゆる要素が必要です。
エチュードを課題に入れることは理解できます。素晴らしい演奏を聴くのはいつでも嬉しいものです。でも今日、エチュードでキャリアを築くわけではないので、何を証明するためなのだろうかと思うことはあります。古典ソナタが満足に弾けなくてもエチュードが弾ければいいのか、といえば大きな疑問が残ります。とはいえこのコンクールではヴィルトゥオーゾ的要素も重要なので、たとえばハイドンのソナタが上手く弾けてもエチュードが今一つであれば高い評価はできません。でも古典を重視するコンクールであればまた別でしょう。
二次予選はどのコンクールでもフリープログラムが多くなります。それによって各ピアニストのパーソナリティやプライオリティが分かりますので、プログラム構成も見ます。ロマン派の大曲や華麗な曲も増えますが、大枠の中で我々はそれを受け入れなければなりません。でも一方向に偏りすぎている例もありますね。恐らくこのピアニストはこのような選曲が合っていて、将来的にこのようなキャリアの方向に進むだろう、それはそれで素晴らしいと思いますが、自分がそのピアニストのリサイタルに行くかどうかはまた別の話です。
課題曲が多すぎると自由がありませんが、あまりに自由すぎると比較するのが難しいので、何を優先するかですね。あるイタリアのコンクールでは、一次予選でベートーヴェンのソナタ(第29番ハンマークラヴィア以外)を弾くようにと50年前に提案したのですが、良く機能しているようで、今もその課題を維持しています。ベートーヴェンのソナタは技術的にも難しいし、様式・形式への理解や音楽性も分かります。バッハについてはそこまで重きを置いていません。ショパンやラフマニノフ、ブラームスなどでポリフォニーが分かりますから。ベートーヴェンのソナタはいつでもプログラムの中心にあります。プログラムは、その人がどういうピアニストであるかという情報を示してくれます。(ベルリン芸大入試課題はバッハ、ベートーヴェン、自由曲)
モーツァルトの協奏曲に関しては、「どのように弾かれるべきか」という見解がそれぞれ違います。ベートーヴェン以上にね。今では、当時の演奏習慣などを誰もが知ることができるので、何も知らない無邪気な演奏は受け入れられません。モーツァルトと電話で話せるわけではないけれど(笑)、これだけ情報網が発達していますから誰でも情報入手はできます。とはいえ、知識を持っていても良い音楽家でなかったり、良い音楽家でも知識を持ってなかったり。ミュージシャンシップと知識が両方あればいいのですが。自作カデンツァはそのピアニストの創造性や価値観が分かるのでいいですね。
年齢層が高いのは良いことですね。審査員は若い才能に高い評価を与えがちですが、彼らがこれから様々な危機を迎えるだろうことを忘れがちです。若い人はまだCarte Blanche(白紙)なのです。我々審査員は責任があるので、才能だけではなく、どこまで到達できているかを見るようにしています。もちろん10代半ばでも達成しているものがあれば比較できます。もし自分がコンクールを創る立場であれば、最年少23歳以上にしたいですね。私が役員を務めているスイス・ファンデーション(奨学金授与など)は、20歳以下の学生には授与しないというルールにしています。
私自身は原則として年齢にはあまり関心がありません。たとえば天才作曲家を例に挙げると、モーツァルトは早熟でしたが、ブルックナーは遅咲きでした。ハイドンも長生きして年齢が長じるにつれて作品が成熟していきました。天才といわれる作曲家ですら、年齢とともに成熟期を迎える人もいました。演奏家にも同じことが言えるでしょう。
6歳の時にピアノを始めましたが、読譜を教わったのはもっと後です。小さい頃は終戦直後でしたし、社会状況も混乱していました。両親は音楽家ではありませんでしたが、自然に音楽に囲まれた環境で育ちました。母親はアマチュアのヴァイオリン奏者で、友人同士で弦楽四重奏を弾くといったことが日常でした。クラシック音楽は日常生活の一部でしたね。また母親は子どもに一切無理強いすることがありませんでしたので、高校までは普通の勉強をしながら、その後自分の意思で音楽の道に進みました。
10歳の時にピアノの先生が変わりました。すでにご高齢で、先生の先生がクララ・シューマンの生徒でした。彼は指揮者でもあったのですが(主に米国で活躍)、指揮の先生がブラームスの友人でした。ですから私にとって、音楽に接することや音楽について語ることはごく自然なことでした。当時レコードはあまりなかったのですが、ラジオ放送をよく聞いていましたね。先生が「今夜、自宅にきて一緒にブルックナーの交響曲第8番を聴かないか?」と誘って下さり、スコアを持って一緒に聴いたこともあります。またカトリック教徒として育ちましたので、教会でオルガンを弾きながら、ハーモニーがどのように響くのかを学びました。
ええ。音楽について語ること、音楽を言葉にして表現することは、ある時期には大事だと思います。物事を深く知覚することができますから。いずれその理解が自分のものになれば、他の曲にも応用することができます。でなければ単なる先生の真似になってしまいます。レッスンでは生徒との対話を大事にしています。彼らの意見にも興味がありますので、まず私が聞くのは「あなたはどう思いますか?」ということ。話したり書いたりすることで、何となく感じるだけでなく、明確に音楽を理解することができます。
アジア出身の生徒はピアノ演奏に関しては長けていますが、音楽理解に関してはヨーロッパの生徒より難しいと感じることがあります。どれだけ時間がかかっても理解してもらえるように努めています。1時間に1ページしか進まないこともありますが、「わかってくれた」と実感する時があります。すると、別の曲にも応用することができるようになります。
ある日本人生徒が、「先生の話していることが最初は分からなかった」と後から告白してくれました。言語の問題だけでなく、音楽の捉え方についてです。ある時、彼女は危機的状況に陥りました。自分は誰なのか、自分はどこで何をすべきなのか・・・というアイデンティティ・クライシスに陥り、弾くことも困難になりました。でもこれは良い兆候だったのです。実は、私はその瞬間を待ち望んでいました。これを乗り越えなければ何も変わりませんから。最初は大変ですが、このようなプロセスが大事だと思っています。
音楽ジャーナリストとして各国を巡り、国際コンクール・音楽祭・海外音楽教育などの取材・調査研究を手がける。『海外の音楽教育ライブリポート』を長期連載中(ピティナHP)。著書に『ハーバードは「音楽」で人を育てる~21世紀の教養を創るアメリカのリベラル・アーツ教育』(アルテスパブリッシング・2015年)、インタビュー集『生徒を伸ばす! ピアノ教材大研究』(ヤマハミュージックメディア・2013年)がある。上智大学外国語学部卒業。在学中に英ランカスター大学へ交換留学し、社会学を学ぶ。一般社団法人全日本ピアノ指導者協会勤務を経て現職。2007年に渡仏し「子どもの可能性を広げるアート教育・フランス編」を1年間連載。ピアノを幼少・学生時代にグレッグ・マーティン、根津栄子両氏に師事。全日本ピアノ指導者協会研究会員、マレーシア・ショパン協会アソシエイトメンバー。 ホームページ:http://www.erikosugano.com/