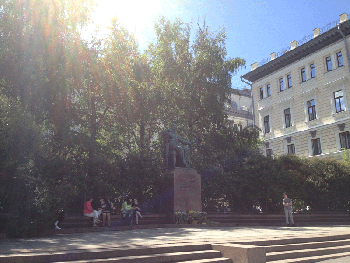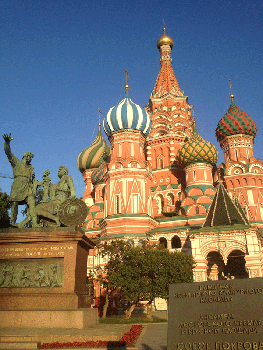チャイコフスキー国際コンクール(1)一次・二次予選ソロを終えて
6月16日からモスクワで開催されているチャイコフスキー国際コンクール。ロシアをはじめ世界中の猛者が集まったピアノ部門は、予備予選を経て、36名が第一次予選(6月16日-20日)に進んだ。ライブおよびアーカイブ視聴はこちらへ!
今回は36名中、10代が2人、20代前半が11名、20代後半-30代が23名(うち30歳以上が10名)と年齢層が高く、国内外でプロ活動しているピアニストも多い。国際コンクールといえば10代後半-20代前半が多い印象だったが、年齢層の幅が明らかに広がってきた。それだけコンクールの存在意義が多様化しているといえる(→参考「国際コンクールの今」)。
今回はいわば「これからアーティストとしてどう伸びていくのか」という試験のようなものといえるだろうか。また「これからアーティストとしてどうありたいか」という自分自身への問いかけでもあり、「アーティストとは何か、何を求めるのか」を聴衆も一緒に考える機会でもある。
一次予選は一人40分-50分以内のソロリサイタルで、まさに実力伯仲であったが、この段階で一気に12名に絞られた。筆者は一次予選途中から聴かせて頂いているが、印象的な演奏もあり、二次に進めなくてもそれぞれに素晴らしい実力者であることは間違いない。それは恐らく予備予選にもいえることだろう。
さて二次予選(6月21日-25日)は前半のソロリサイタル審査を終え、これからモーツァルト協奏曲審査を迎える。※すでに終了して二次予選結果が出ました。
まず地元ロシア勢は、いずれも恵まれた身体と鍛えぬかれたテクニックを兼ね備えている。さすが多くの素晴らしい音楽家を生み出してきたロシア、小さい頃から良い教育を受けてきたことを伺わせる。軽やかに美しく難曲を弾きこなす姿は、まさにお見事!最年少16歳ハリトノフ(Daniel Kharitonov)の伸びやかなテクニックや自然で優雅な音楽的感性は、これから引出しが増えるにしたがってさらに成長するだろう。マスレーエフ(Dmitry Masleev)はすらっとした身体から幅広いディナーミクと弾力性ある音が出て、弱音も極めて美しい。二次予選では標題音楽が多かったが、いずれもくっきり情景が浮かぶような素晴らしい描写を聞かせてくれた。また深く分厚い音と弱音の対比で奥行きある情景を描くゲニューシャス(Lucas Geniusas)、ラシュコフスキー(Ilya Rashkovsky)も透き通るような音で美しい瞬間を見せてくれた。二次には進めなかったがディミトリ・シシュキン(Dmitry Sishukin)の芯のある美しい音も印象的。
優れた詩的な表現を見せてくれたのはメドヴェデフ(Nikolay Medvedev)。特に一次予選で情感豊かなチャイコフスキーのグランド・ソナタOp.37第2楽章、二次予選のドビュッシー『雪の上の足跡』(前奏曲第1巻より)はピアノを打鍵しているようには聞こえず、雪の中を歩いているような冷たさと柔らかい感触を感じさせる。各楽章の性格を効果的に描き分けたハイドンのソナタHob.XVI/24(一次予選)も素晴らしかった。ジョージ・リー(George Li)は曲によって出来が異なるが、第一次予選のベートーヴェン・ソナタ32番の全体解釈とそこから導き出される音には深遠さもあり、一転して第二次予選のリスト・ハンガリー狂詩曲2番では、リズムの特徴をよく出しながら男声と女声が即興的に絡み合うような雰囲気が醸し出された。またリード・テツロフ(Reed Tetzloff)のジョージ・グリフィスのピアノソナタA.85、カプースチンの変奏曲Op.41などの洗練された演奏、時代性をあえて打ち消したような現代的プログラムもユニークだった。
曲の解釈で魅せたのは、トゥルパノフ(Mikhail Turpanov)である。第二次予選ではスクリャービンのソナタ7番、そしてメシアンの「愛の教会の眼差し」(『幼子イエスに注ぐ20の眼差し』より)は、第二次世界大戦中のドイツ占領下のフランスで書かれた曲だが、キリスト生誕の場面を描きながら、まるで破壊の閃光が放たれる中から新しい光が創造されるかのような表現に、鬼気迫るものがあった。また二次には進めなかったが、音楽の姿を真摯に見つめるアレクセイ・ペトロフ(Alexei Petrov)の演奏も印象に残る。ベートーヴェンのソナタ3番はチェンバロのように軽い打鍵、ラフマニノフ音の絵Op.39-5の深い打鍵と、プログラム全体で対比してみせた。またチャイコフスキーのドゥムカは、深い悲哀や儚くも美しい旋律が胸を打った。
そして、鋭い解釈と研ぎ澄まされた表現で驚かされたのはフランス出身ルカ・デバルグ(Lucas Debargue)!第一次予選でも独特の世界観を見せていたが、二次予選では特にニコライ・メトネルのソナタ第1番は別次元の音楽を聴かせてくれた。冒頭で提示されるテーマが哲学的な自問問答のように何度も繰り返され、そのたびに深く心の底をのぞき、真理を求めて彷徨う姿が想像される。左手の空虚五度が、なんとも含みのある空虚さなのである。倒錯的でもあり、幻惑的でもあり、啓示的でもある、メトネルの知られざる素顔を見た気がする。続くラヴェル「夜のガスパール」も、水の煌めきのような精霊に誘惑され水底に引き込まれそうになる「オンディーヌ」から始まり、恐怖が静かに迫る「絞首台」、「スカルボ」まで、息をつかせぬ展開であった。音はイメージから導き出される。そのことを改めて感じさせてくれる演奏だった。そして、聴衆の拍手とブラボーは数分間鳴りやまなかった。
※「今こそ音楽を!」連載は7月より再開します。
音楽ジャーナリストとして各国を巡り、国際コンクール・音楽祭・海外音楽教育などの取材・調査研究を手がける。『海外の音楽教育ライブリポート』を長期連載中(ピティナHP)。著書に『ハーバードは「音楽」で人を育てる~21世紀の教養を創るアメリカのリベラル・アーツ教育』(アルテスパブリッシング・2015年)、インタビュー集『生徒を伸ばす! ピアノ教材大研究』(ヤマハミュージックメディア・2013年)がある。上智大学外国語学部卒業。在学中に英ランカスター大学へ交換留学し、社会学を学ぶ。一般社団法人全日本ピアノ指導者協会勤務を経て現職。2007年に渡仏し「子どもの可能性を広げるアート教育・フランス編」を1年間連載。ピアノを幼少・学生時代にグレッグ・マーティン、根津栄子両氏に師事。全日本ピアノ指導者協会研究会員、マレーシア・ショパン協会アソシエイトメンバー。 ホームページ:http://www.erikosugano.com/