ヴァン・クライバーン国際コンクール(2)予選I:音から伝わるもの

第14回ヴァン・クライバーン国際コンクールが5月24日に幕開けた。このコンクールは1962年第1回大会を皮切りに4年毎に行われ、過去の優勝者・入賞者にはニコライ・ペトロフ、ミハイル・ヴォスクレセンスキー(1962年)、ラドゥ・ルプー(1966年優勝)、クリスティーナ・オルティーズ(1969年優勝)、野島稔(1969年)、アレクサンダー・トラーゼ(1977年)、クリスチャン・ツァハリアス(1973年)、アレクセイ・スルタノフ(1989年優勝)、ジョン・ナカマツ(1997年優勝)、最近ではアレキサンダー・コブリン(2005年優勝)、辻井伸行、ハオチェン・ザン(2009年優勝)など、実力派ピアニストを輩出している。特に前回2009年大会での辻井伸行さんの優勝は日本でも大いに話題になり、その活躍ぶりは誰もが知るところである。
今年は30名がDVD審査を通過し、ここテキサス州フォートワースのステージに姿を現した。実力者が勢ぞろいである。日本からは最年少参加者となる阪田知樹さんが出場。筆者は聴けなかったが、すでに会場でもその予選第1回目の演奏が評判になっている(第2回目リサイタルは、日本時間29日9:30より)。さて、今年はどんなピアニストの頭上に栄冠が輝くだろうか?
※コンクールのライブ配信、およびオンデマンド映像はこちらから!
●音楽から何を発見し、引き出し、どう伝えてくれるのか
さて予選は45分間リサイタルが2回行われ、27日午前で全員が1回目のリサイタルを終えた。筆者は26日から聴いているが、ここまでの印象(5月26日・27日)をまとめてみたい。
まず、コンクール全体レベルは大変高い。30名それぞれが素晴らしい才能を持ち、真摯に音楽と向き合っている。どれだけの練習時間を積み重ねてきたのか、楽譜と向き合ったのか、自分の音を探し求めたのか、その努力の成果が45分間に凝集されている。弾けて当たり前というレベルがここまで高まると、その磨かれたテクニックや感性を生かして、「音楽から何を発見し、引き出し、それをどう伝えてくれるのか」が問われてくる。
そこで今回は「音から伝わるもの」「曲全体から伝わるもの」「プログラムから伝わるもの」という3つの観点から、それぞれ特徴があった演奏や印象に残った演奏を挙げてみたい。
●音から伝わるもの
なぜ曲の解釈や演奏によって「美しい」以上のものが感じられるのだろうか、なぜ「大きい音」と「壮大な音」は違うのだろうか。音色や音質は曲全体の解釈から導き出されてくるものであり、たとえば「美しい音」や「音の強弱」も相対的なものである。何をもって美しいというか、それは曲が求める美しさをどう捉えるのかによる。

中でもフランソワ・デュモン(Francois Dumont, France)のモーツァルト・ソナタ イ短調K.310は印象的であった。和声進行を意識しながら、どんな微細な表情の変化も聞き逃さない。左手の伴奏も旋律を彩る背景色のように、一音一音色を変化させて全体の表情を創っていく。第2楽章も劇の第2幕が始まるかのような冒頭から、また一つ一つの音やフレーズと向き合い、対話するように音楽が進められていった。美しさの中に、儚さ、脆さ、哀しみ、軽やかさ、モーツァルトが含ませた様々な表情や感情が1枚1枚解き明かされていく。どれもが美しい瞬間でありながら、彼のはなぜ「綺麗な音」だけで終わらないのだろうか?「モーツァルトの左手は単なる伴奏ではありません。特にこのソナタは左手の支えが重要だと思います」と本人は言う。
またラヴェル『夜のガスパール』の『オンディーヌ』でも左手のパッセージがつくる雰囲気の描き方が見事(左手の達人!)。一転して『絞首台』では終始鳴らされる変ロ音が、鐘の音から絞首台の刃の音までを連想させ、そこにひやりとした質感をもたらしていた。『スカルボ』では冒頭のフレーズ間の休符を十分にとり、重低音を厳かに響かせてその先を予感させる。一音だけで深い世界を呼び覚ませる、そんな演奏だった。
マルチン・コジャック(Marcin Koziak, Poland)は、ベートーヴェンのソナタ第8番Op.13ハ短調(悲愴ソナタ)からブラームスのソナタ第1番ハ長調という流れ。ベートーヴェンは丁寧なアプローチながら幾分控え気味の表現であったが、一転ブラームスでは冒頭から堂々とした主題の提示、そして哀愁漂う旋律も感情豊かに歌わせる。ブラームスはベートーヴェンを敬愛し影響を受けていたが、2曲目のブラームスはベートーヴェンの影響が残りつつも、音質・音量・感情表現は豊かになり、当時の楽器の規模や時代様式の変化を相対的に感じさせてくれた。彼は予選第1回目*のプログラムも相互に関連性を持たせた構成になっているようである。
スキピオーネ・サンジョヴァンニ(Scipione Sangiovanni, Italy)も構築力がある。ベートーヴェンのソナタ第3番Op.2からフランクへ、『前奏曲、コラールとフーガ』では教会のパイプオルガンのような響きを演出した。強打しても、決して奥行のないフォルテやフォルテシモではない。バスの豊かな重量感が和音に立体感を与え、それが空間の広がりを背後に感じさせた。音量が大きければよいということではなく、いかに立体的に多層的に響きを作りだすのかが、音楽全体の壮大さや壮麗さに繋がっていくと感じた。
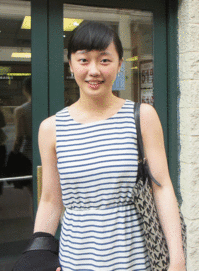
またフェイフェイ・トン(Fei-Fei Dong, China)は、本人が音楽の一瞬一瞬に感動しながら弾いているのが伝わってくる。「ホロヴィッツの演奏が好きで選びました」というクレメンティのソナタOp.25-5嬰ヘ長調も、シューマン『8つのノベレッテ』8番(嬰へ短調Op.21-8)も、要所要所で透き通った煌びやかな美しい音で魅了する。最も生きていたのはショパンのロンド 変ホ長調Op.16だろうか。これはたしか2010年ショパン国際コンクールでも聴いたが、フレージングも自然になり、その中で遊び心や可憐さを存分に生かしている。音楽に心から共感して一体化しているためか、青年ショパンの感性の煌めきや美しい音との出会いの瞬間に、我々も立ち会った気持ちになる。
*マルチン・コジャックは今回が予選第2回目プログラムで、第1回目は終了しました。訂正してお詫び致します。
音楽ジャーナリストとして各国を巡り、国際コンクール・音楽祭・海外音楽教育などの取材・調査研究を手がける。『海外の音楽教育ライブリポート』を長期連載中(ピティナHP)。著書に『ハーバードは「音楽」で人を育てる~21世紀の教養を創るアメリカのリベラル・アーツ教育』(アルテスパブリッシング・2015年)、インタビュー集『生徒を伸ばす! ピアノ教材大研究』(ヤマハミュージックメディア・2013年)がある。上智大学外国語学部卒業。在学中に英ランカスター大学へ交換留学し、社会学を学ぶ。一般社団法人全日本ピアノ指導者協会勤務を経て現職。2007年に渡仏し「子どもの可能性を広げるアート教育・フランス編」を1年間連載。ピアノを幼少・学生時代にグレッグ・マーティン、根津栄子両氏に師事。全日本ピアノ指導者協会研究会員、マレーシア・ショパン協会アソシエイトメンバー。 ホームページ:http://www.erikosugano.com/
