第23回 岡田暁生『ピアニストになりたい!19世紀 もう一つの音楽史』

最近、ようやく学業に一区切りがついて少し時間ができたので、気になっていた本を何冊かまとめて読むことができた。今回は、息抜きのつもりで、そのうちの一冊を紹介する。
『ピアニストになりたい!19世紀 もう一つの音楽史』(岡田暁生著、春秋社、2008年)―昨年10月、こんなタイトルの本が最近出版された。なぜ今回この本を取り上げるかといえば、この連載でこれまで扱ってきた問題が取り上げられているからだ。たとえば、カルクブレンナーのメソッドおよび手導器、音楽院におけるコンクールの話、等々。この本の特色は、19世紀から20世紀初期にかけてのピアノ教育におけるメカニカルな側面を、近代産業社会の発達という文脈の中に位置づけている点にある。岡田は、フンメルやカルクブレンナー、フェティス/モシェレス等によって出版された19世紀のピアノ・メソッドを、練習音型を羅列する「ハノン流の指ドリル」の原型と位置付けたうえで、次のように述べている。
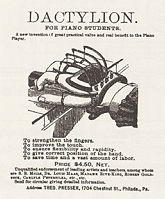
このように全体を部分へと還元して生産の効率化を図るという初期産業化社会の発想が、音楽作品から抽出・還元された様々な音型を並べるというメソッドの発想と同じであるという観点は興味深い。さらに、特定の練習音型を徹底的に弾きこませる19世紀のスパルタ式ピアノ教育が、「流れるような動きを単純動作=指/脚の上げ下ろしに分解し、それを不自然なまでにゆっくりと反復させることで、筋肉を鍛え強化する」(111頁)、軍隊教練の発想をモデルとしているという指摘も面白い。こうして「マッチョな指」を鍛え上げるために開発された様々な器具や手の手術法が、「指強化器具と人体改造の思想」と題された第4章で紹介される。サイボーグを思わせるH. エルツの「ダクティリオン」(右図、128頁挿絵より転載)など、豊富な挿絵が読者の目を楽しませてくれる。
身体を機械的・自動的にする近代ピアノ教育史を概観したうえで、この本の著者が最終的に、たどりつく一つの独創的な見解は、第6章「『分解・反復・強化』という深層構造」の項目に見出される。岡田によれば、ハイドンとベートーヴェンの作曲法に見出される「主題加工thematische Arbeit」(「主題労作」と訳されることが多い)の技法、つまり主題旋律を幾つかのモチーフに分解・断片化し、それらを組み合わせたり、対照させたりすることによって作品を構築する手法(ベートーヴェンの第5交響曲第1楽章を思い浮かべるとわかりやすい)は、18世紀末から19世紀の工場労働や軍隊教練、体操理論などにみられる「小さな要素へと分解しようとする近代社会の性癖」(203頁)を反映した「優れて近代市民社会の音楽に固有のもの」(202~203頁)である。こうした部分の反復のプロセスを、岡田はシューマンやブラームスのいわゆる「発展的変奏」技法やモチーフを執拗に反復するヴァーグナーの主題法に見出している。音楽から抽出された練習音型という「部分」の反復練習によって指を強化し、「音楽という『全体』」(205頁)を獲得するという、19世紀のピアノ訓練法は、まさにシューマンやブラームスに見られる同時代の代表的音楽作法と同じ原理に基づいているというのがこの著者の結論である。
しかし、この結論は、あくまで仮説として提示されているにすぎず、検証の余地は多分に残されている。たとえば、ハイドンの主題労作の手法は本当に「近代市民社会の音楽に固有」なものと言い切れるだろうか。岡田の指摘するように、ハイドンが晩年、産業化社会を先導していたイギリスで書いた一連の交響曲には、主題労作の手法が認められるので、これらの作品には「勤勉な
だが、残念なことに、細部にこだわると、誤った記述が少なからず目につく。最も問題が多いのは「勝ち組になるのは誰?」と題された第2章だ。パリ音楽院のコンクールについて記述したこの章の「コンクールの始まり」という項目は、偶然にも本連載で前回扱った『ル・ピアニスト』という当時の音楽雑誌記事が扱われている(記事の詳細については第22回参照)。以下に、瑣末なものから重大なものまで、問題点を列挙する。
| (1) | 岡田は、この記事が1833年に出版されたとしている(41頁)が、これは1834年の誤りである。1834年のコンクールの様子を記した記事が33年に出版されるはずがない。 | ||||||||||||||||||
| (2) | 前回の連載では、男子クラスの講評を扱ったが、この本では女子クラスの講評が引用されている。問題は、この講評の著者が誰か、という点にある。岡田は、これを審査員として招かれた「アンリ・ベルティーニ(一七九八~一八七六)の採点評」としているが、それは誤りで、この評は、この年のコンクールを取材した『ル・ピアニスト』の記者によるものだ。なんとなれば、記事にはこの講評を指す言葉として、しばしば「筆者[すなわち記者]の覚書nos tablette」という語が用いられているからだ(1)。この記者は、不自然に受賞者が続出するパリ音楽院のコンクールに疑問を抱き、これを第三者的な視点から評価することで、この年の受賞者が本当に受賞に相応しかったのかを議論している。 | ||||||||||||||||||
| (3) | この年の女子クラスのコンクール課題曲は、「モシュレスのピアノ協奏曲(番号は不明)だった」としているが、記事にはこの協奏曲が「第3番」であったと明記されている 。(2) | ||||||||||||||||||
| (4) | 女子クラス出場者の演奏評が記事から引用されているが、そのひとつに「デューク嬢」(42頁)の演奏に関する評がある。これは単純な誤読で、正しくは「ドラーク嬢Madmoiselle Drake」である。ドラークOdinne-Henriette Drake(1815- ?)はこの年のコンクールで一等賞を獲得した。 | ||||||||||||||||||
| (5) | 1834年の音楽院コンクール男子の部に、岡田は「若き日のアルカン」が出場していたとしている。『ル・ピアニスト』の記事に登場するこの「アルカン」を、岡田はアルカンCharles-Valentin Alkan (1813-1888)と見做しているが(この本の索引には「アルカン、ヴァランタン」と記されている)、これは誤りで、このコンクールに出ていたのはアルカン四兄弟のうち三男のマキシム・アルカンである(マキシムに対する記者の評は、前回連載記事を参照のこと。彼はあまり芳しくない評価を受けている)。ちなみに、パリ音楽院には5人のアルカンがいた。すなわち、長女セルスト(1812-1897)、長男ヴァランタン、次男エルンスト (1816-1876)、三男マキシム、四男ナポレオン (1826-1906)、五男ギュスターヴ (1827-1882) というアルカン一姉四兄弟である。第5章で岡田はこの誤りを踏襲して、「[ヴァランタン・]アルカンも音楽院に通っていて、試験の成績があまり良くなかった」(156頁)と述べている。ヴァランタン・アルカンの名誉のためにも、この記述は訂正が望まれる。ちなみにヴァランタンは、1823年、弱冠9歳で音楽院コンクールの一等賞を獲得した俊才だった。 | ||||||||||||||||||
| (6) | これまでもこの連載で扱ったヅィメルマンPierre-Josef-Guillaume Zimmermanという19世紀前半の音楽院ピアノ科教授の説明箇所に、「ピエール=ジョゼフ・ツィンマーマン(一七八五~一八五三年 アダム(3)に次ぐパリ音楽院二代目のピアノ教授」と書かれている(43頁)。この記述は不適切である。当時、リ音楽院には男子クラスと女子クラスがそれぞれ複数存在していた。たとえば、1816年ころから1840年ころにかけては、主に次のような教授のクラスが存在していた(青欄は男子クラス、赤欄は女子クラス)。
|
第1章と第2章は、近代化社会とメカニックなピアノ教練という、この本の中心的話題への導入部であって、上に指摘したような欠点が全体の論旨に致命傷を与えるわけではない。しかし、この種の資料の誤読は、著者の信頼を損ないかねないものだ。
第5章「聞くも涙、語るも涙の音楽院」の小項目「ソリストへの志向」(154~157頁)において、岡田は19世紀の音楽学校を「野心に満ちたソリスト志望の若者が行くところというより、国の文化事業に必要な人材を組織的に育成する場所として意図されていた」(154頁)と位置づけ、19世紀の音楽学校からは「一流の」ピアニストは殆ど出なかったと述べている。こうして、〈二流ピアニストを育成するアカデミー⇔アカデミーにとらわれない一流[天才]のピアニスト〉という二元的図式が創られる。このような想定は、この本にしばしば垣間見られる。たとえば第3章「毎日ドレドレミレミレ」の冒頭には次のような文が見られる。「たとえ周囲から変則的といわれようが、天才は常に本能で自分の流儀を見出す」「天才にマニュアルは要らない。天才は生まれつき自分自身の型をもっている」(59頁)。マニュアルや規則というのは、音楽院に代表される教育機関のメタファーである。
〈アカデミズム=二流⇔非アカデミズム=一流/天才〉という二分法を正当化するために、岡田は「フンメルやツェルニー、カルクブレンナーやモシュレス、ショパンやリストやタールベルク[...]モシュコフスキに至るまで、誰も音楽学校に通っていなかった」と述べている(155~156頁)。ここでカルクブレンナーは音楽学校に通っていなかったことになっているが、これは誤りで、本連載第7回で述べたように、彼は、1799年から1801年にかけて、音楽院でアダン に師事した「アカデミー側」の人である。ショパンにしてもワルシャワ時代、同地の音楽院の院長だったエルスネルに師事している。つまり、〈アカデミズム=二流⇔非アカデミズム=一流/天才〉という二分法は、この著作においてはかなり恣意的なものといえる。
岡田は、パリ音楽院は「少々事情が違う」と述べてはいるものの、結局は、19世紀後半の音楽院教授、マルモンテルやディエメは「どちらかといえばアカデミズムの人であり」、あるいは音楽院出身の「プランテにしても果たしてビューローやタウジッヒやダルベーアに匹敵する格のピアニストだったかどうか」疑問視している。ところで、この著者は一体何を基準に過去のピアニストを格付けしているのだろうか?彼のこのような評価は、厳密な調査・検討を経ていないので、曖昧・不明瞭だ。学術論文ばかりでなく一般向けの書物においても、否、多くの人の目に触れる一般向けの書物にこそ、厳密な検証が必要なのではないか。考証が不十分な事例は、時に疑わしい推論をもたらす。
今後この連載で扱っていくが、パリ音楽院では世紀前半に教授を務めたヅィメルマンの指導のもと、卓越した近代的テクニックと音楽的表現の両立を目指すフランスのエコールが誕生する。その旗手となったのはヴァランタン・アルカンをはじめ、ルイ・ラコンブ、エミル・プリュダン、アントワーヌ=フランソワ・マルモンテルたちである。19世紀のアカデミズムが「一流」を生まなかったように見えるのは、単に彼らの作品が知られていないからにすぎない。非アカデミズム「天才」ショパンの周囲にいたアカデミズムにおける「天才」たちは、まだ十分学術的評価の対象にはなっていない。今後の連載において、彼らの存在意義を明らかにしていきたい。
(1) "Concours du Conservatoire de musique" in Le Pianiste, ( Meudon: Imprimerie de J. Delacour), 1834, no.11, n.d. pp.164-165.
(2) Ibid., p. 164.
(3) 書評筆者注:ルイ・アダンは、この本では「アダム」と表記されている。フランス語の発音に忠実な表記は前者である。人名の日本語表記については人によって見解が分かれるが、筆者は、原則としてその人物の出身地または活躍地の発音に忠実な表記を用いるべきだと考える。たとえば、音楽院でピアノ科教授を務めていたフランス人のP.-J. Zimmermanの場合は、「ツィンマーマン」ではなく「ヅィメルマン」などと表記するのが良いと思う。同様にパリ音楽院教授だった、Henri Herzの場合は「ヘルツ」ではなく「エルツ」とすべきであろう。とはいえ人名の発音には例外が多いので、ネイティヴ・スピーカーの専門家の意見を参考にするのが良いと思う。
金沢市出身。東京藝術大学音楽学部楽理科卒業、同大学修士課程を経て、2016年に博士論文「パリ国立音楽院ピアノ科における教育――制度、レパートリー、美学(1841~1889)」(東京藝術大学)で博士号(音楽学)を最高成績(秀)で取得。在学中に安宅賞、アカンサス賞受賞、平山郁夫文化芸術賞を受賞。2010年から2012まで日本学術振興会特別研究員(DC2)を務める。2010年に渡仏、2013年パリ第4大学音楽学修士号(Master2)取得、2016年、博士論文Pierre Joseph Guillaume Zimmerman (1785-1853) : l’homme, le pédagogue, le musicienでパリ=ソルボンヌ大学の博士課程(音楽学・音楽学)を最短の2年かつ審査員満場一致の最高成績(mention très honorable avec félicitations du jury)で修了。19世紀のフランス・ピアノ音楽ならびにピアノ教育史に関する研究が高く評価され、国内外で論文が出版されている。2015年、日本学術振興会より育志賞を受ける。これまでにカワイ出版より校訂楽譜『アルカン・ピアノ曲集』(2巻, 2013年)、『ル・クーペ ピアノ曲集』(2016年)などを出版。日仏両国で19世紀の作曲家を紹介する演奏会企画を行う他、ピティナ・ウェブサイト上で連載、『ピアノ曲事典』の副編集長として執筆・編集に携わっている。一般社団法人全日本ピアノ指導者協会研究会員、日本音楽学会、地中海学会会員。

