2010ショパン音楽祭(2)~ショパンは、バロックや古典をどう聴いたのか
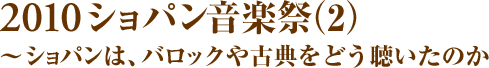

この音楽祭の目的の一つは、ショパンの時代を再現することでもある。ショパンはバッハを始めヘンデルやグルックなども、客をもてなすために演奏していたという。ショパンはバロックや古典派音楽にどのようなインスピレーションを受けたのだろうか?それはルバートや装飾法といった技術的な要素だけではないだろう。
中世、ルネサンス、バロック、古典、ロマン派・・・時代が変わっても人は変わらず、人間の心理や思考の発露としての音楽に、時代を問わず共感させられることが多くある。一方、表現様式は時代に伴って変化し、前時代の要素を少しずつ継承しながら、新しい様式が生み出されてきた。
ショパンが生まれたのは古典派からロマン派に至る流れの中であり、18世紀半ばから文学の世界で主流になりつつあったロマン主義の影響が、いよいよ本格化した頃である。そしてショパンの才能によって、情と理が完璧に融合した、類まれなる美意識の世界が築き上げられた。今回はそんなショパンが生きた19世紀前半という時代の視点を踏まえて、バロック・古典派音楽を聴いてみた。

ジョヴァンニ・アントニーニ指揮(Giovanni Antonini) 、イル・ジャルディーノ・アルモニコ(Il Giardino Armonico)のコンサートを二夜に渡って聴いた。この楽団は1985年にアントニーニらがミラノで旗揚げし、主に17・18世紀の作品をピリオド楽器を使って演奏する。チェチリア・バルトリやマグダレナ・コジェナーなどの一流声楽家との共演も多い。バロック、古典派を中心に組まれたプログラムは、歴史的変遷も踏まえた興味深いものだった。
8月9日はバロック中心のプログラム。ジョヴァンニ・バティスタ・フォンタナ(Giovanni Battista Fontana/1571-1630)、タルクィニオ・メルラ(Tarquinio Merula/1595-1665)、 ヨハン・ハインリヒ・シュメルツァー(Johann Heinrich Schmelzer /1620-1680)といった初期バロック作品と、ゲオルク・フィリップ・テレマン(Georg Philipp Telemann/1681-1767)、アントニオ・ヴィヴァルディ(Antonio Vivaldi/1678-1741) 。普段あまり演奏されない作曲家も登場し、バロックの軽やかな音色とリズムに彩られた自由な世界が広がる。

プログラム冒頭のフォンタナは、旋律、バス、通奏低音をそれぞれ担当する3つの楽器で構成されるトリオ形式を発明した人。またメルラはトリオ形式にシャンコンヌやフォリアなどの舞踊を融合させ、さらにヴァイオリン奏者であったシュメルツァーは、ヴィルトォーゾ的な旋律パートでトリオ形式を発展させた。こうした歴史的な変化を踏まえたプログラム構成が面白く、演奏もvn.オノトリを中心に冴えたハーモニーを聴かせる。
プログラム後半はテレマンとヴィヴァルディの協奏曲。明確なアーティキュレーション、充実した低音部と通奏低音、楽章間のコントラスト、各楽器の掛け合い、華麗な装飾音から祝祭のような賑やかさも伝わる。
ふと、ヴィヴァルディの協奏曲にある仕掛けがなされていることに気づく。カデンツをよく聴くと、途中からショパンの前奏曲に・・!「もしバロックの作曲家がショパンを知っていたら?」という粋なジョークに、見事にヴィヴァルディに溶け込んだ、ショパンの微笑まで見えるようであった。客席からも思わず笑いと拍手が起こった。

この日はイル・ジャルディーノ団員が小編成で登場、ヴァイオリンのエンリコ・オノフリを中心に、リュートやハープシコード(チェンバロ)が際立つ演奏であった。また指揮者ジョヴァンニ・アントニーニが華麗なリコーダー演奏も披露し、素晴らしい指揮者であるとともに、優れたリコーダー奏者であることを印象づけた。
前日8月8日は古典が中心で、ヨセフ・マルティン・クラウス(Joseph Martin Kraus/1756-1792)オリンピア序曲、ハイドンの交響曲第49番 「受難」、ボッケリーニの交響曲Op.12-4 「悪魔の家」、ロッシーニ歌劇「アルジェのイタリア女」序曲、ショパンのポーランド民謡による大幻想曲。
奇しくもモーツァルトと同年に生まれ、モーツァルトの死から1年後に亡くなったクラウスは、ドイツで生まれスウェーデン王宮内で活躍した。「スウェーデンのモーツァルト」とも呼ばれ、生前はグルックやマルティニ神父などとも接触があり、ハイドンには交響曲を献呈している。当日演奏された「オリンピア序曲」の冒頭には一見リュリかと思わせるフレーズがあり、演奏会の幕開けにふさわしい優雅さも称えた1曲だった。またボッケリーニの田園風で優雅な表現の中に見られる悪魔の演出、ハイドンの交響曲で見られる嘆きの感情など、イル・ジャルディーノの演奏は、イタリア人らしく陽気でありながら、誠実さとほどよい情感が感じられる。フレーズの収め方が洗練されており、全体として優美さを保ちつつも、躍動感に満ち溢れていた。指揮者アントニーニの指先と身体から弾むようにリズムが湧き出て、その指揮を信頼する奏者たちに伝わっているのがわかる。素晴らしい信頼感で結ばれた楽団と感じた。

白眉はロッシーニの「アルジェのイタリア女」(1813)。序曲のテーマには2本のリコーダーが登場した。通常はオーボエとフルート(クラリネットも)で奏されるが、リコーダーを使うと、高く明るい音質に心地よい温かさが加わる。
この曲は若干21歳だったロッシーニの名を一躍有名にした作品で、ショパンが生まれた3年後に作曲された。ポーランドでは1826年に初演され、当時の音楽評論家からは「複雑な音楽が好きな輩にとっては面白く感じられないだろう。それほど深淵ではなく、単にうっとりとさせてくれる音楽」と評され、そしてショパンは友人に対して「お洒落なもの」といった表現を使っている。ショパンが「流行」以上の価値を見出したかどうかは不明だが、同時代人であったロッシーニが作った大らかで陽気な旋律や歌いまわしは、ベリーニ同様、ショパンを魅了したのは間違いない。ロッシーニのオペラ作品は当時ヨーロッパ・米国でも流行し、ベートーヴェンなど同時代の音楽家からも多くの支持を得ていたが、ショパンもその例に漏れず、「歌劇『シンデレラ』の主題によるフルートとピアノのための変奏曲」を作曲している。

このように青年期のショパンは、他作曲家による作品をテーマにいくつか曲を書いているが、特に有名なのが「モーツァルトの歌劇『ドン・ジョヴァンニ』の中のアリア『お手をどうぞ(ラ・チ・ダレム・ラ・マーノ)』の主題による変奏曲op.2」。(この日演奏される予定だったが、ピアニストの変更によりキャンセル)
ショパンが他人のテーマを借用して作った曲は、どことなく祝祭的な雰囲気を纏う長調が多い。ショパンは人物模写が得意だったが、これもショパンお得意の'遊び'だったのだろうか。あるいは自分にない感覚表現を模倣することによって、感性の領域を広げようと試みたのだろうか。

プログラムの最後は、ショパンが18才の時に作曲した「ポーランド民謡による大幻想曲」、ステージには1848年製エラールが運び込まれた。この日、本来出演予定だったデヤン・ラジッチ(クロアチア)に代わって、ポーランド出身マグダレーナ・リサックが急遽代役として出演することが当日会場で案内された。リサックは1995年ショパン国際コンクールで第6位に入賞した経歴を持つ。なんと3日前、バカンス中に突然電話がかかり、急遽出演を打診されたというリサックだが、落ち着き払ってピアノに向かった。ピリオド楽器は初めて弾いたそうだが、確かに打鍵すると鍵盤に指が触れる音が目立ち、特に右手高音部の響きがあまり伝わってこない。しかし中音部はまろやかに鳴り、民族舞踊風のリズムや旋法を用いた旋律など、ショパン独特の魅力を余すことなく表現した。
2日に渡るイル・ジャルディーノの演奏は、ピリオド楽器を用いながらバロック音楽の豊かな色彩感と自由闊達さを体現し、また古典派から初期ロマン派にかけての歴史的変遷を踏まえたプログラムによって、より繊細な感情表現がショパンの音楽世界へと繋がる流れを見せてくれた。ショパン・フェスティバルの「当時を再現する」試みは、大成功だったと思う。

