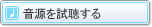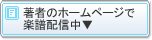第43回「小夜想曲―魅惑」
実験的要素を意欲的に取り入れたり、悪ふざけを詰め込んだりして、一風変わった作品をたくさん残したアルカン。しかし彼の初期の作品を見ると、出発点はある意味ごく真っ当だったということがよくわかります。
20歳ごろまでのアルカンの作品には華麗な技巧を前面に押し出したオペラアリアの変奏曲などが多く、ピアノ奏者として当時のヴィルトゥオーゾ礼賛の風潮に憧れていた彼の姿が浮き彫りになっています。
作品15の『悲愴な様式による3つの曲(思い出)』などは、既にアルカンらしい挑戦的な書法で染め上げられてはいますが、内容はと言えば(まず間違いなく)失恋を題材に取った、いかにもロマン派のど真ん中といった風情の音楽。
アルカンは当時の音楽に馴染めなかったから、あんなにロマン派主流に対して斜に構えたような曲を作っていたんだろう、なんて考えてしまいそうですが、本当はそういうことではないんじゃないか。ロマン派の王道に憧れ続けてもいたのではないか、と私は勝手に想像しています。アルカンはただ、面白さを見つけるのに貪欲で正直で、だから流行のスタイルだけに乗っかるだけでは満足できなかったのだ、と。
晩年にアルカン自身がピアニストとして開いたコンサートのプログラムが残っているのですが、この選曲が相当に興味深い。アルカンは「本当に素晴らしい曲しか弾かない演奏会」と公言していたそうなので、このラインナップを見れば、彼の音楽の趣味がはっきりとわかるはずです。
大バッハ、モーツァルト、ベートーヴェン、シューベルト、メンデルスゾーン、シューマンといった馴染みのドイツ系作曲家たち。クープラン、スカルラッティ、ラモーといったバロック時代の鍵盤音楽奏者たち。チェルニー、モシェレスなど練習曲の作者。そしてショパンにアルカン自身。あとはヘンデル、フンメル、ヴェーバー、クレメンティ、グルック、フィールド、ケスラー、サン=サーンス。
古い物は200年近く昔の作品から、後輩にあたる若者の音楽まで、別け隔てなく接していたアルカンの態度が目に浮かびます。近い世代では、メンデルスゾーン、シューマン、ショパンなどが選ばれていてリストはいないこと、そして何よりここに選ばれた作曲家の名前のほとんどが現代の我々にとっても馴染み深いものであることなど、示唆に富んだプログラムです。
同時代の作曲家の中で、アルカンが最も敬愛していたのはたぶんショパンで間違いない。生前の交流や、コンサートで取り上げている曲の数などからはそのように見受けられます。アルカン自身はショパンのような繊細で感傷的な音楽をあまり好んで作りはしませんでしたが、恐らくは自分がショパンと同じ方向性で勝負しても決して勝てないことを知っていたからでしょう。それに、自分の中の私的・詩的な部分をショパンのように歌い上げるには、アルカンはシャイに過ぎたのだ、と私は思います。
アルカンは演奏会でフィールドの曲も取り上げています。フィールドはショパンに影響を与えた作曲家として知られ、甘い旋律で聴かせる「ノクターン」を得意としていました。やっぱりアルカンはそういう甘々の音楽も実は好きだったんだ、ということ。ただ、そういう気分に完全に浸ろうとしても、ついつい自制が働いてしまって駄目だったんでしょう。そこがアルカンの良さでもあり、勿体なさでもあったように感じられます。
アルカン自身も「ノクターン」と名のつく曲はいくつか書いているのですが、その中には「蟋蟀(コオロギ)」なんて副題をつけた作品もあったりする。なんだか自分の心の中の感傷だけに陶酔し切れないアルカンの態度の表れのように思えてなりません。
今回の曲「小夜想曲――魅惑」はしかし、純粋に陶酔的な「ノクターン」の世界。『エスキス』という大きな曲集の中だからこそ、恥ずかしがらずに少しはこういう面を出せたのかな、などと想像します。
この曲を演奏するときには、ショパンの曲同様、指先のタッチをどれだけ繊細にコントロールできるかが勝負になります。中間部の長調になった "dolcissimo" 部分は特にそう。こういう場面こそ、お腹にきちんと力を入れて支える必要があります。お腹に力を入れたぶん、肩甲骨から手首までは力を抜いて柔らかく、自由自在に動ける状態を保ってください。旋律はせめて4小節のフレーズがきちんとまとまるように、アゴーギクに注意しながら歌うこと。最後、長調の分散和音から一瞬で短調へ変わりますが、これはおいしい聴かせどころです。大切に弾きましょう。
ではではまた次回、「有頂天」にて。