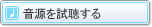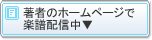第42回「5声の小さな歌」
生真面目さ。アルカンを語るのに欠かせない言葉です。
いやいや、なんか奇人ぽいし曲も変なの多いし、真面目ではないだろう、と考えてしまいそうなんですが、自信を持って言わせていただきます。彼はものすごく真面目だ。いっけん暴挙としか思えないことも、全部きちんと考えてから「あえて」やっているのに違いないのです。楽譜を見ればわかります。彼がどれほど思慮深かったか、そしてどれほど几帳面であったか。
たとえば、警告の臨時記号の振り方。警告の臨時記号というのは、記譜法のルールの上では臨時記号をつける必要がない箇所に、間違い防止を目的として念のためにつけられる臨時記号を指します。アルカンはこの警告の臨時記号を決して怠らない。それどころか、そこまで念を押さなくてもいいんじゃないか、というくらい、同じ小節内であっても繰り返しつけたりするのです。この連載のための楽譜を作りながら、毎回のように「親切な警告だなぁ」と感心させられています。
前回の「異名同音」の楽譜を見ていただければわかりやすいでしょう。あの曲は臨時記号が多く複雑ですから、そのぶん特に正確を期したのは当然のことかもしれません。が、それにしたって、たとえば10小節目などはすべての音符に臨時記号をつけるという念の入れようではありませんか。普通の感覚なら最後の和音の臨時記号なんかは書かないと思います。
アルカンの曲には、たまに「トリプル#」のような特殊な臨時記号が出てくる場面も見受けられます。たとえば「ドのトリプル#」は「レの#」か「ミの♭」に相当するので、簡単に書きたければどちらかで代用するのが普通です。というより、一般的にはそんな臨時記号が出てこないように#の調と♭の調を書き換える。そうした方が書きやすく、読みやすいからです。
しかし彼は、その場面は#で書くべき転調だ、と判断すればためらわずにトリプル#だって使ってしまう。はっきりとした自分の判断基準に従い、律儀な記譜をしていることがよくわかります。
臨時記号だけではありません。声部ごとにクレッシェンド、デクレッシェンドの記号をいくつも書いたりとか、長い音符にまとめてしまえば手間が少なくなるような場面でも、拍子による記譜の基本を守るためにきっちり全部タイで書いたりとか、そんな場面にいくらでも出くわします。
第2曲の「スタッカーティッシモ」なども良い例だと思う。これ、普通の感覚ならスタッカートの点を打つのがめんどくさくなって、途中で "simile" とでも書いて終わりにしたっておかしくない。でも、アルカンはあくまで全部の音符に点をつけることを選ぶんです。楽譜としての見た目の美しさやわかりやすさ、完成度までも大事にしていたからでしょう。だから手抜きはしない。彼はそういう人なのです。
ところで、アルカンの譜面をパッと見ていちばん気になるのは、彼独自の小節線の使い方でしょう。曲の途中になぜか終止線が繰り返し出てくる。初めて見た人は、これには大いに戸惑うことでしょう。私もそうでした。よそで見たことのない書き方なので、どう解釈すべきなのか即座にはわからない。しかし、譜読みを進めていくとだんだん、「これはほかの作曲家も真似すべき優れた改良なのではないか」などと思えてくる。
思いつきでやっていることでは決してありません。音楽の構造を一目で演奏者に伝えられるように、という強い目的意識のもと、アルカンがあえて人と違う小節線の使い方を選び、出版各社にも忠実な浄書を頼んでいたことは明らかです。曲中の終止線の多用は、10代半ばで出版された最初期の作品から首尾一貫して続けられている。まだ少年と呼べそうな年齢にして既に、彼は記譜法について考え抜き、独自のアイディアを育んでいたのです。
さて今回の「5声の小さな歌」ですが、これは音楽の作りそのものからアルカンの丁寧さ、真面目さが読み取れる作品。タイトル通り、本当に男女5人で歌えるように注意深く作られているんです。音域もちょうど歌いやすい範囲にとどめられている。結局のところ実際はピアノで弾くわけだから、ちょっとくらいはみ出ていたって構わないはずなんですが、アルカンはその辺りきっちり自分で決めて守る。彼の筋の通し方、私はとても好きです。
ですから、演奏の際には何よりもまず自分の中で人の声をイメージしてみましょう。5つのパートすべてをきちんと歌にできるよう、横の流れをしっかり捕まえること。また、sfがついている場所も決して器楽的にならぬよう、唐突なアクセントは避けましょう。
それではまた。次回のタイトルは「小夜想曲――魅惑」です。