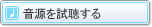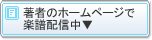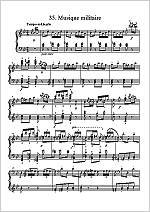第35回「軍楽」
作曲家は何のために曲を書くのか? これは突き詰めると哲学的な問いにもなり得ます。もちろん、お金のためだとか、仕事で頼まれたからだとか、そういうレベルの答え方もできる。けれども、もっと本質的なことまで考え出せば、音楽とは何ぞや、芸術とは何ぞや、みたいな問いにまでつながってしまいます。
しかし作曲家はあくまで曲を作らねばならない存在。哲学的問答のために思考をぐるぐる巡らせていたって作曲はできません。だから、結局はその時代に支配的な思想だとか、需要だとか、あるいは自身の生活だとかに影響されて、バランスの取れた場所で自分を納得させることになる。でなければ、「何のために」なんてことは一切考えず、呼吸するように音楽をする。
実際のところ、何のために音楽をやるのか、などという問いにきちんと答えるのは不可能なのです。それはもう色々な要素があって、あるひとりの作曲家だって、いつも同じように音楽を生み出すわけではない。たとえば自身の苦悩に耐え切れぬ余り、その痛みを作曲に向けるような場合もあれば、知り合いのお嬢様を喜ばせるために、ちょっとした可愛らしい小品を作ってみることだってある。
だから、何のためにやる、なんてことで深刻に悩むよりは、「音楽でこんな遊びもできるのか!」という発見をどんどん重ねて、そのことを純粋に楽しむのが正しい態度じゃあなかろうか――と、そんな考え方が現在では支配的になってきたように感じます。たとえば現代音楽の中にはアイディア勝負のジョークみたいな曲もたくさんありますよね。
ただし、そんな自由な発想が生まれ得たのは、現代だからこそ、というのも確かです。さまざまな時代を通過し、それぞれの時代の思想のもと極致を目指した先人たちの成果を見渡してこそ、我々が悟ることのできた真実なのでしょう。
それでも、アルカンという作曲家について考えたとき、彼が音楽というものに向かう態度は不思議と現代的であるように思えるのです。
ロマン派の時代には、音楽は精神世界や感情を表現し、それを伝達するものとして扱われる傾向にありました。それこそが目指すべき場所であり、音楽芸術の高みだというのがだいたいの共通認識だった。
それと同時に、ロマン派はヴィルトゥオーゾたちの時代でもあった。圧倒的な器楽演奏の技巧で聴衆を熱狂させることに腐心する人があとを絶たなかった。
俗っぽいとさえ思われる派手な技巧と、精神世界の掘り下げという要素が複雑に絡み合い、色とりどりで華やかな音楽世界が生み出されていった、音楽芸術にとって熱狂と興奮に包まれた時代だったと言えるでしょう。
しかしその一方、音楽におけるロマン主義は、ユーモアだとか滑稽なものなどとはどうもうまく相容れなかった、という印象が強いのです。たとえばシューマンなどは「フモール(≒ユーモア)」という概念をたいそう愛していたにも関わらず、彼の音楽からユーモアを読み取るのは難しく、努力を要することであるように思います。
そんな中、アルカンは軽妙なユーモアを忘れるこがなかった。アルカンの曲には必ずどこかしらツッコみどころがある、と言い切ってもあながち間違いではありません。音楽にユーモアをこめようとしても何故だか深刻路線に行ってしまいがちだったロマン派の空気の中、アルカンは圧倒的に「滑稽」を体現した作曲家だったのではないでしょうか。
今回の「軍楽」などは滑稽そのもの。軍楽隊による金管バリバリの合奏をパロディにした音楽なのですが、なんだか高音がぶら下がっていたり、調和を無視して力任せに吹いてみたり、ひどい出来の演奏だという表現がしこたま盛り込まれています。曲のテンポ表示は「お決まりのテンポで」だし、最後の方には「耳障りに」などという指示まで書く徹底ぶり。音楽でこんな意地悪なジョークまでできてしまうのです。楽しいね!
不出来な演奏を揶揄した作品とはいえ、ピアノ演奏自体は、もちろんしっかり歯切れ良くパリッと弾きこなすことが必要です。合奏をピアノ独奏で再現しているわけで、リストやラヴェル寄りの技巧的な書法も出てきます。分厚い和音の連続なども多いので、それらを掴むときの指のバネをよく意識すること。練習曲として弾きこなし、その上で「滑稽」さが演出できれば言うことなしです。音楽の流れや横のつながりより、唐突さや縦のリズムを強調してみましょう。
次回は「小トッカータ」。いよいよ第3巻の最後の曲となります。